ドッグフードの選び方を説明したサイトや記事は多々ありますが、パピー(幼犬)・成犬・シニア犬(老犬)、いわゆるライフステージによって、フード選びで気をつけないといけないポイントは異なります。
というのも、それぞれのライフステージで、必要になるカロリーも栄養素も、代謝量も違うのは当然ですし、人間も歳と共に食べる量が変わったり、ダイエットしたくても思うように体重を落とせなかったり、体質の変化がありますよね?
それと同じで、シニア犬を飼われている方が、一般的な成犬(特に若年層)向けに書かれているフード選びのポイントを参考にしていると、愛犬に思わぬトラブルや不調が起こりかねません。

特にシニア期は、これまでの暮らし方も影響してきます
そこで今回は「シニア犬」に特化して、
をご紹介していきます。
なお、当サイトのシニア期の認識は、こちらの記事でご紹介していますので、読み進めていく前にご一読いただけると幸いです。

正しい情報を愛犬に活かしてあげましょう♪
また、ここでご紹介するお話は、あくまで「一般的にこうなる」「こういう対策ができる」という内容といけないポイントが出てくるはずです。
個体差があるので仕方がないことなのですが、当サイトでは、それぞれのわんちゃんの体質を考慮し、その子のためだけのフードのご提案やサポートが可能ですので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。※ 当サイトのアドバイスは有料です。無料で相談に回答するものではありません。
(※お問い合わせについて:当サイトからのメールが迷惑メールに振り分けられることがあるので、お手数ですが、返信がないと思われた方は、迷惑メールボックスもご確認ください)
成犬からシニア犬(老犬)になると起きる変化や不調とは?

愛犬にはいつまでも健康で元気に過ごしていてほしいものですが、人間にも老化があるように、犬も月齢と共に老化現象が出てきます。
ここでは、どういった症状が出てくるのか・なぜそうなるのかなどをまとめてみましたので、「いつかは愛犬に起こりえることかも?」と考えながら、読み進めてみてください。
ただし、どういったペース・どういったタイミングで、どういった老化による症状が出てくるのかは、
など、シニア期になるまでの暮らし方によっても異なりますし、小型犬と大型犬のライフステージや老いに対する考え方も異なりますし、何歳になったらこうなるなどの定義はありません。
ですので、これからご紹介する内容は、「こういうことが起こりえるんだな」というふうに、思っておいていただければ幸いです。(※必ずこうなるというわけではありません。)
あるいは、すでにシニア期に突入している(もしくはそろそろシニア期に近づいている)わんちゃんを飼われているのであれば、

うちもこういう症状出てるから、シニアなんだな
と、愛犬の今の体の具合を再確認する機会になるでしょうし、その他ここでご紹介するような症状が出る可能性もあるんだと事前準備をする、もしくは、そういった症状が出ないよう対策をとるなどをしておきましょう!
知っているのと、知らないのとでは対応が全然変わってくると思いますし、飼い主さんも心に余裕を持って対応していけるはずです♪
関節が弱ってくる・関節周りを気にする・運動量の低下(動きたがらない)
シニア期になると、関節を保護する成分(コンドロイチン・グルコサミン)の生成が鈍くなっていき、関節の痛みが出やすくなってきます。そのため、立ち上がる動作が昔よりも遅くなったり、立ち上がりにくそうな素振りが見えたりするかもしれません。
あるいは、歩いている時に関節を気にしているような様子も出てくることもあります。片足を上げたり、痛そうにしたり。犬種やこれまでの運動量によっては、脱臼しやすくなる子もいるかもしれません。
そしてそれに伴って、意欲も低下して散歩などの運動量も落ちてしまったり、寝ている時間が増えたりもします。散歩に行きたがらない、距離を歩こうとしないというのは、関節に痛みを感じているからなのでしょう。
筋力の低下・体力の低下による涙やけや視力低下、トイレの頻度の変化

シニア期になって運動量が減ると、筋力も落ちてきます。ですので、これまでほど激しい遊びもできなく(しなく)なってくるでしょうし、散歩の距離も短くなってきたりと、体力も落ちてくるのは当然のことです。
しかし、筋力の低下によって起こる諸症状はそれだけではありません。筋力が低下することで、目の下が徐々にたるんできて、涙の量を調整する筋肉も弱くなり、涙やけが出やすくなってしまったり、トイレの我慢ができなくなってきたり…。
視力も落ちて、目のトラブルなども起きやすくなってくることも…。筋力が落ちるということは、運動以外にも、さまざまな症状が出る原因になるのですね。
新陳代謝の低下による肥満・肥満による不調や病気・免疫機能の低下

運動量が減って、さらに筋力もなくなってくるということは、新陳代謝も悪くなります。1日に必要なカロリーも減ってくるということです。そのため、これまでと同量のフードを食べていると、言うまでもなく太ってしまいます。
また、人間でも言われることですが、犬にとっても「肥満は万病のもと」です。実際に、肥満の犬の寿命はそうでない犬よりも短いというデータもあります。

しかもシニアにダイエットさせるのは大変!
具体的な病気・不調をご紹介しますと、
| 関節炎 | 体重の重さから、関節に負担がかかって痛みが出る |
| 糖尿病 | 肥満によって尿中に糖が排泄される |
| 循環器疾患 | 余分な肉や脂肪が気管などを圧迫し、呼吸がしづらくなる |
| 尿路結石 | 尿のシュウ酸の濃度が高くなり結石になる |
などがありますが、他にもたくさんの不調や病気があり、もう書き切れません…。
それに加えて、そもそもシニアになると免疫力も落ちてきますし、さらに肥満になると免疫機能が低下するというデータもあり、こうなってしまうと踏んだり蹴ったりとでもいいましょうか…。

病気になりやすいのに、回復力は落ちるという悪循環
そして、少し触れましたが、シニア期になると筋力も減る手前、運動量を増やしてダイエットをさせるという選択肢はなくなってしまいます。もし運動をできる子だとしても、関節も弱ってきているので、運動量を増やすダイエットはお勧めしません。
そうなってしまうと、給餌量の調整や与えるフードを替えるなどで体重管理するしかなくなってしまいます。
ただ、この年代になってくると、いずれにしてもダイエットは簡単なことではなく、長丁場になってくると思いますので、飼い主さんもわんちゃんも気長にダイエットに挑むようにしなかればなりません。
毛質の変化(毛が硬くなる・毛艶が落ちる)・抜け毛・毛の退色
人間が歳と共に白髪になるように、犬もシニアになってくると、被毛に変化が出てきます。
具体的には、人間と同じような内容ですが、
などがあり、見た目にも触った時も毛質にも変化が出てくることでしょう。
原因は、被毛を維持するための筋力が低下することや、運動量の低下による血行不良、被毛を美しく保つめに必要なコラーゲン生成の低下、栄養素の吸収率の低下、ホルモン量の低下などがあります。
食欲の低下・噛む力の低下・歯や歯茎の病気、それに伴う瘦せすぎな体型

太りやすくもなる反面、食欲が落ちてきて痩せ気味になってしまう子もいます。代謝が落ちている上に、運動量も減っているので、空腹感を感じにくいのでしょうね。
また、これまで歯磨きをしっかりしてこなかった場合などには、歯や歯茎の不調(歯周病など)から、本当は食べたいのに、痛くて噛めない・食べられない…という状態になってしまう危険も…。これは本当に可哀想なケースです。
噛む力が弱くても食べやすい、ウェットフードなどで対処することもできますが、ウェットフードは総カロリーが低いので、必要なカロリー分食べようと思うと、量もたくさん食べないといけませんし、ドライフードよりもコストもかかります。

あまりに高いと継続が厳しいですよね…
しかも、ウェットフードはその特性から、歯や歯茎に挟まってしまったり、くっついてしまったりしやすいため、やっぱり歯磨きはしてあげなければなりません。歯の健康は維持できず、悪化する一途になってしまうわけで…。
結果、不健康な状態になってしまうということには変わりありませんよね。さらに、歯周病などの細菌が体内に回ってしまい、さらなる病気や不調を招く危険もあります。口臭がきつくなっている場合なども注意が必要です。
そうならないためにも、パピー期から歯磨きをできるようにしておいた方がよいでしょう。もし、どうしても歯磨きができず、歯周病も酷いようであれば、歯石取りを動物病院でしてもらうという選択肢も考えてみてくださいね。
消化器官の不調による、便の回数や量・色・形状などの変化
シニア犬になると、消化器官の活動も鈍くなってきます。そりゃもう何年も使っている器官ですから、徐々に疲れも出てくるのも仕方ありません。結果、思うように栄養を体内に取り込めなくなってしまいます。
さらに、運動量も減っているため、血流も悪くなり、体温が低下しやすくなり、お腹は冷えて壊しやすくもなりますし、便のサイクルが変わってきたり、色や硬さなども変わってきたりすることも…。シニアになると下痢・軟便が増えがちです。
それ以外にも、腸内の善玉菌が減ってきて、お腹を壊してしまう子もいますし、ストレスなどにも弱くなってきますので、自律神経が乱れて、ストレス性のお腹の不調が出てしまう子もいます。
水分摂取量の低下・皮膚の変化(カサカサ・カイカイ・フケ・たるみ)

運動量も減り、体も冷えやすくなってしまうと、水分を飲もうとすることも少なくなってしまいます。シニア犬の場合は特に、喉が渇いたと感じる中枢神経も鈍くなってきているため、水分摂取量が減ってしまい、脱水しやすい状態になっているので注意しなければなりません。
シニア犬を飼われている方は、水分を愛犬がしっかり取っているか気に留めてあげてください。愛犬のごはんの量は把握しているのに、水分摂取量はそこまで把握していない方も案外多いものなんですよ。
また、水分は生命維持に欠かせないもので、水がなければ食べたものを溶解し、栄養分を体内に運ぶ役割ができません。水が足りないと、さまざまところに不調が出てしまう原因になります。

体内の水分を5~6%失うと、皮膚に変化が出始めます
体内の水分量が不足すると、肌も乾燥してカサカサになってきますし、弾力もなくなってたるんで戻らないようになってしまうこともありますし、お伝えしているとおり、最悪の場合、命にかかわることも…。
急性の脱水でもなければ、徐々に変化が出てくるので、飼い主さんも「水も飲んでるし大丈夫だろう」と思って見ていても、実際は必要量は摂取できておらず、水分が足りない状態になっていることもありえます。
また、消化が悪くなっていることでお腹を壊して脱水気味になっているケースもありますし、腎臓病や膀胱炎などの泌尿器トラブルによる脱水症状もありえるため、しっかり水分を取らせて上げるようにしてくださいね。
病気や手術などの経験から嗜好が変わったり、食欲が落ちることも…
パピーやまだ若年層の成犬の場合と、シニア期に入っている犬の場合では、回復力もまったくことなります。先ほどお伝えしたように、免疫力なども落ちてきていますし、傷口の治りが遅かったり、不調からの復帰に時間がかかるとようになってきたりもします。
また、どうしても体力も落ちてきているため、元気もなくなってくると、運動量も減りますし、疲れやすくもなり、犬自身も今までのようにたくさん遊べなくなっていることを寂しく思っているのかもしれません。
そんなこともあり、犬にもメンタルの病気ってあるんですが、かまってちゃんになってきたり…食べなくなってすねたり…これまで大好きだったものも急に食べなくなったり…と、予期せぬ変化が出てくることもあり得る話です。
これまで食べてきたものによっては尿路トラブルなどを併発することも…

シニア期の体調は、これまで食べてきたもの、運動量などの集大成と言ってもかごんではありません。そのため、バランスが悪い食生活をしてきた子の場合は、尿石・結石症などになるリスクも高まります。
これまで人間の食べ物を食べてきた子や、おやつなど与えすぎな子などは、こういった腎臓トラブルが多くなりますので、注意してあげましょう。
犬が食べても良いものであったとしても、率先して与える必要はないものもあります。「犬は〇〇を食べてもいい」という情報があったとしても、あくまで食べてもいいというだけで、与えましょうということではないのでご注意くださいね。
シニア犬(老犬)におすすめなドッグフードの選び方とは?

パピーにはパピーにふさわしいフードの選び方、成犬には成犬にふさわしいフードの選び方があるように、シニア犬にも適したフードの選び方があります。
しかし、ひと言で「シニア犬」「老犬」といっても、ひとまとめに考えるの危険です。

シニアはこうって決めつけない!
なぜなら、元気なシニア犬もいれば、かなりの高齢に該当するハイシニアもいますし、体質もそれぞれ違うから。これまでどれくらい運動をしてきて、どれくらい筋力があるのかも違いますし、太る子もいれば痩せる子もいますし…。
そのため、シニアだからこう!という考えに縛られることなく、愛犬の状態を見ながら、必要そうな要素だけをピックアップしていだければ幸いです。
高たんぱく過ぎないフードを!ただし筋力維持の適度にたんぱく質は必要
高たんぱくなフードは、心臓を含む筋肉に負担をかけていまいます。機能が低下してきているシニア犬にはふさわしくありません。とはいえ、筋肉維持にはたんぱく質は必要です。そのため低過ぎず、適度なたんぱく質量のものを与えましょう。
高タンパクすぎるものの場合、運動量が減って筋肉に変換されなかったたんぱく質は、脂肪になってしまい肥満の原因になります。あまりに高タンパクなのは危険です。
これまでの運動量や、現時点での運動量や筋肉量にもよりますが、パッケージに記載されている成分表を見て、25%前後のものまでにとどめ、たんぱく質30%以上のものなどは避けておいたほうがベター。

高たんぱく=良いという考えはNG
しかし、そうはいっても、繰り返しにはなりますが、今ある筋力を維持するためには、たんぱく質は必要です。そのため、低たんぱくが良いという話でもありません。
AAFCOの定義では、成犬は18.0%以上のたんぱく質が理想とされているため、少なくとも18%以上のフードを選ぶようにしましょう。アレルギーなどがない限り、主原料はフレッシュミートのものだと効率よく消化吸収もできると思いますよ♪
あくまでこれは、運動量も代謝も落ちている傾向があるわんちゃんへの対処法です。シニア期になっても、運動量も代謝も衰えず、活発な子もいますので、そういった子はこれに限りませんので、ご注意くださいね。(それでもたんぱく質30%以上は避けてください)
脂質を抑えたフードを選ぼう!ただし脂質は皮膚・被毛ケアに必要不可欠

高たんぱく過ぎると残った成分が脂質に変換されて太る原因になるため、脂質や糖質が高いフードは、代謝が落ちているシニア犬(老犬)には太るリスクになります。そのため、あまり脂質が高くないフードを選ぶようにしましょう。
しかし、脂質は決して悪いものではありませんし、むしろ生きる上では必要なものです。特に、皮膚ケアにも脂質は欠かせません。そのため、いくらシニア犬は太りやすくなる・代謝が落ちるとはいっても、現時点で肥満気味でもない限りは
などはする必要はないので、焦ってフードを替えなくても大丈夫ですよ♪

脂質源にフォーカスしてください
それよりも、「脂質=太る」という考えではなく、脂質がなに由来なのかということを重視して、健康的に良きるために必要な脂質(良質な脂質)を効率よく摂取できるフードを選びましょう。
たとえば、サーモン、サーモンオイル、ココナッツオイル、ひまわり油、亜麻仁オイルなどは、皮膚や被毛ケアに欠かせない脂質源です。こういった脂質は避ける必要はありません。皮膚が乾燥してきたり、被毛の質が変化したりするシニア期には摂取しておきた方が良い脂質です。
そのため、ドッグフードの成分表を確認して、脂質が高過ぎるものは避けつつも、かといって、低ければいいというわけではないため、原材料を確認して、どういった原材料から脂質が摂取できるのかもチェックして選ぶようにしましょう!
食欲と運動量に合わせて低カロリーフード・高カロリーフードを選ぼう
シニア犬(老犬)になると起きる変化や不調でもお伝えしたように、わんちゃんの体質・これまでの生活スタイル(散歩量など)や筋肉量・病気や不調の有無などによって、体重や食欲に相反する変化が起こります。
具体的には、以下のような太りやすい子と痩せてしまいやすい子の2タイプがあり、これは個体差があるので、飼い主さんが判断してあげてください。
| 太ってしまいやすいタイプ | 痩せてしまいやすいタイプ |
| 食欲が衰えない | 食欲が落ちた |
| 筋量が少なく代謝が落ちる | 筋量が多く代謝が落ちない |
| 運動量が落ちる | 運動量が落ちない |

日々のケアで飼い主さんも感じると思います
どちらに該当するわんちゃんなのかによって、おすすめするフードが正反対になります。
太りやすい条件がある子の場合は、これまでと同じ量を食べても太りにくいよう、カロリーが低めのフードを選ぶようにしましょう。反対に、食欲が落ちてあまり食べなくなっている場合には、カロリー高めのもので、少量食べるだけでも栄養が取れるフードを食べるのが理想的です。
ウェットフードは嗜好性が高く低カロリーなので、食欲やカロリーのコントロールに使いやすいアイテムだと思います。ぜひお試しくださいね。
関節ケアやアイケアに良い成分が配合されているフードを選ぼう

人間も同じですが、犬もシニアになると関節の軟骨成分が減って、痛みが出やすくなります。そのため、関節ケアにいい、
- コンドロイチン
- グルコサミン
- コラーゲン
などが原材料に配合されているフードを選ぶようにしましょう。もしくは、サプリメントでも構いませんよ♪
日々の生活で関節は擦り減ってしまいますが、歳と共に関節の動きをスムーズにする軟骨成分の生成は減っていきます。だったら、食べ物から直接とるのが一番です。

コラーゲンは被毛ケアや皮膚ケアにも良いのでオススメです
また、目の周りの筋力も落ちてきますので、涙量をうまく調整することができなくなってきます。シニアになると、涙が出ている子(涙やけが出ている子)も多くなってきますので、目のケアもしておくといいですね!
目のトラブルはシニア犬特有のもの以外にも、皮膚炎で赤くなってしまったり、病気(白内障や結膜炎など)だったりもあるので、年齢故の症状か別なトラブルがあるのかは見極める必要があります。
なお、犬のアイケアに有効な成分は、
- ルテイン
- アントシアニン
- アスタキサンチン
- DHA
などがあります。

目に良い成分は人間と同じです♪
関節ケアと同じく、犬用のサプリメントで摂取させるのも良いですし、上記の成分を多く含む食材が配合されているフードを優先的に選ぶのもありです♪
具体例を挙げますと、
| ルテイン | プルーン・小松菜・ほうれん草 など |
| アントシアニン | ビルベリーやブルーベリー、ラズベリーなどのベリー系 |
| アスタキサンチン | サーモン、鯛な、加熱した海老(※生海老は犬にはNG) |
| DHA | イワシやサバなどの青魚 |
などがあります。トッピングアイテムとして使用するのもいいですね。
上手に愛犬の食生活に上手にとり入れてあげましょう!
フードの粒があまり大きすぎないもの・ふやかしやすい形状のもの
噛む力が落ちてきている(口を開ける力が弱くなっている)、歯や歯茎が弱ってきているなどが起こりやすいシニア期ですので、フードの粒があまり大きくないものを選ぶようにしましょう。
また、もう1点考えておきたいのは、
などのケースもあること。
犬はフードを噛んで食べずに飲み込んで食べる習性があるのですが、消化器も弱ってきていますので、これまでどおりに食べていると、お腹を壊す子もいます。

消化スピードもゆっくりになるからね
そのため、消化にやさしく胃腸の負担を軽減できるようフードをふやかして与えるのもありです!そういった時にも対応できるように、ふやかしやすい形状のフードだとさらに使いやすいと思いますよ♪
小粒のものや、平たいコイン型のものも良いと思いますし、本当に食欲も落ちて、食べようともしてくれない、あるいは食べること自体がしんどそうであれば、ドライフードじゃなくてもウェットフードなどを与えても構いません。
嗜好性が高く、口・歯・胃腸に負担が少ないという意味では、硬いフード・粒の大きいフードなどよりも、小さい・柔らかいものの方が愛犬の体には負担はかからないというメリットがあることを、頭の片隅に置いておいてくださいね♪
整腸作用が期待できる成分が配合されている・繊維のバランスが良い
 .
.
消化器が弱ってきて、お腹の調子が悪くなる子もいます。そのため、オリゴ糖やビフィズス菌、乳酸菌などが配合されていて、繊維とのバランスが良いフードを選んであげましょう。
ただし、腸内環境には個体差があるので、ここでのお話は、どの子にでもおすすめするわけではありません。愛犬の様子を見ながら調整するようにしてください。(乳酸菌・ビフィズス菌がなに由来なのかによっては、食物アレルギーがある子もいるためです。)
上記のことを念頭に続けていきましょう。お腹の調子を安定させる(整腸作用)には、プレバイオテイクスとプロバイオティクスのバランスが重要です。

繊維は胃腸の病気の予防に必要なものなんだよ
プレバイオティクス(prebiotics)は難消化性のオリゴ糖や食物繊維など、食べても胃や小腸で分解・吸収されずに大腸に到達し、大腸に生息する微生物の餌になる食品成分のこと。
引用元:日経バイオテク
ちなみに、ドッグフードによく配合されている繊維が多い食材は、ごぼう・サツマイモ・玄米(米類や麦類の穀類全般)・セロリ・キャベツ・白菜・ケルプ(わかめなどの海草類)などがあります。ほかにもたくさんありますので、あくまで一例に過ぎませんが。
そして、最近日本でもよく聞く、プロバイオティクスという言葉ですが、正しく説明できるでしょうか?念のため定義を確認しておきましょう。

プレバイオ?プロバイオ?ややこしいね…
プロバイオティクス(probiotics)がある。こちらはビフィズス菌や乳酸菌などの人の腸に存在する善玉菌そのものを摂取する。プロバイオティクス食品としては、生きた菌が含まれるヨーグルトなどの発酵乳、納豆などがある。
引用元:日経バイオテク
よく聞くビフィズス菌や乳酸菌の総称がプロバイオティクスというニュアンスの覚え方でもかまいません。
なお、プロバイオティクスはもともと、体内に存在する微生物と同じ(ラクト○○というネーミングのもの)や、類似した微生物のことを指します。そのため、体内にいる菌が順調に働いていれば、追加摂取はしなくても問題ない成分です。

現代の食生活では腸内環境が乱れがちだから、追加摂取するんだ
そして、プレバイオテイクスだけでもなく、プロバイオティクスだけでもなく、双方のバランスが良い状態で摂取できると、なお一層効率的に腸内環境改善が期待できます。そのため、どちらか一方だけ摂取するのではなく、バランスよく摂取できることが理想的です。
生きた有用菌=プロバイオティクスと、有用菌の栄養源=プレバイオテイクスを摂取して、相乗効果でお腹を安定した状態に保ちます。
しかし、最初にお伝えしたように、腸内環境は個体差があるので、よかれと思って乳酸菌を与えていたら、繊維などのプレバイオテイクスとのバランスがよくなく、お腹を壊してしまう子もいますので、少しずつ愛犬の様子を見ながら試してみるといいですね。
新陳代謝UP・運動パフォーマンスが向上する成分が配合されている
これはマストではありませんが、筋力や代謝が落ちないように、運動パフォーマンスを向上させる効果が期待できる成分が配合されているフードを選ぶとなおよしです。
たとえば、
があります。
BCAAとは、Branched Chain Amino Acid(分岐鎖アミノ酸)の頭文字で、バリン、ロイシン、イソロイシンのことを指し、筋量維持に欠かせないアミノ酸なので、運動した分の体力をキープしたいシニア世代にはおすすめです。

鶏肉・まぐろ・かつお・牛肉などにBCAAは多いよ!
また、L-カルニチンは脂肪をエネルギーに変える働きがあり、筋肉を動かすエネルギー源になるため、肥満抑制にも有効です。羊肉(ラム)や、牛肉、貝類などにも含まれていますが、羊肉がダントツに多く含まれていますよ。
ただ、いずれも、適量であれば体に良いのですが、過剰に摂取してしまうと不調の原因になりかねないので、よかれと思ってたくさん摂取し過ぎてしまわないよう注意してくださいね。
おわりに
ここでご紹介した内容はあくまで、こういったケースもあります・こういう対処法もありますという参考に過ぎません。老化の状態によっては、どんな工夫をしても、食べようともしない子も出てくるでしょうし、年齢を重ねても全然元気な子もいます。
状況はその子その子によって違ってきますので、ご自身の愛犬に見合うものを採用いただければ幸いです。
なお、当サイトでは、それぞれのわんちゃんの体質を考慮し、その子のためだけのフードのご提案やサポートもできます。(※特定の疾患などがある場合はお断りすることもございますが)気になる方はお気軽にお問い合わせくださいね♪











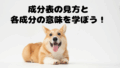
コメント