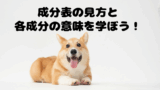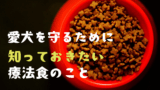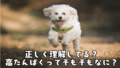愛犬の体を作るドッグフード。体調も食いつきも安定していて、ずっと同じものを与えている方もいるでしょうが、
- 体調に合わなくなった、アレルギーのような症状が出た
- 食いつきが悪くなった、食べない
- フードの値上げで今与えているフードを継続するのは、金銭的に厳しくなってきた
- フードローテーションをしたい
- ライフステージの変化
- 体型や体質の変化
- 愛犬に色んなものを食べさせたい
など、さまざまな理由からドッグフードを替える機会もあると思います。
でも、切り替え方の失敗や、切り替えるフード選びの失敗によって、うまくいかずに結局もとのフードに戻してしまったり、愛犬に負担をかけてしまったりしているケースも…。その原因の大半が、犬が悪いのではなく、飼い主さんに問題があるケースが多いものです。

フードの切り替えもフード選びも迷いますよね~
できれば飼い主の切り替え方が悪いせいで、犬に負担をかけることは避けたいでしょうし、失敗したことによって、食べてくれなくなり、用意したフードも処分しないといけなくなるなんて、いい気はしませんよね。そこで今回は、飼い主さんがやってしまいがちな、
についてご紹介していきます。該当することがないかチェックしてみましょう。
なお、体質や年齢、健康状態によっては注意したいポイントは異なります。個体差がありますし、愛犬の体質の確認の仕方を教えてほしい・相談したいという方は、お気軽にお問い合わせくださいね!※ 当サイトのアドバイスは有料です。無料で相談に回答するものではありません。
(※当サイトからのメールが迷惑メールに振り分けられることがあるので、返信がないと思った場合には、迷惑メールボックスもご確認ください)
飼い主さんがやりがちなフードを切り替える時の失敗例【9選】
はじめに、飼い主さんがやってしまいがちな、ドッグフードの切り替えの失敗例を9つご紹介します。
フードの切り替えなんて、そんなに気にしていないという方もいるかもしれません。しかし、犬からしてみたら、フードが替わるのはとても重要なこと。警戒心が強い子の場合、食べなくなってしまう可能性もあります。

うちはなんでも食べるから大丈夫!
と軽く考えていたら、嫌がって食べなかったり、お腹を壊したり…。もしくは、これまで大丈夫だったからと安心していても、愛犬の年齢や体調、原材料などによっては、フードの替え方ひとつで不調をきたす原因にもなりかねません。
あなたのご家庭では、これからご紹介するような、犬を苦しめる危険のあるフードの切り替え方をやっていないでしょうか?確認してみてください。
失敗例①ある日突然、いきなり新しいドッグフードに切り替えた

「よし、フードがなくなったし、今日から新しいフードにしよう!」
…と、ある日突然新しいフードに切り替えるような、大胆な切り替え方をしていないでしょうか?ほかにも、サンプルなどで少量だからと、いきなり一気に一食分(もしくは、数十グラム)を与えるとか…。
このやり方、食いつきが悪い子(好き嫌いが多い・フードジプシー含む)や、お腹が弱い子、アレルギー体質な子にはおすすめできるやり方ではありません。
ドッグフードを替える時は、どんな子であっても、少量ずつを混ぜ込みながら切り替えるのが基本です。もしくは何粒か(多くてもひと握り分程度)を試しに与えてみるなど。詳しくは以下の「ドッグフードの正しい切り替え方!注意点やコツを学ぶ!」という記事にも記載してありますが、
という具合に、徐々に配合比率を替えながら、最終的に完全に新しいフードに移行していくようにしてください。

急にフードが変わると胃腸がびっくりしちゃう!
突然フードを替えることで、胃腸に負担がかかることがあるので、理想は10日~15日かけていくと安心です。胃腸がもとから弱い子、胃腸が丈夫ではないパピー期・シニア期、フードジプシー、初めてフードを替える時などは、さらに気長にゆっくり時間をかけてもいいでしょう。
新しいフードの方が愛犬に合うだろうから、早く替えたい…早く効果を見たい…うちはなんでも食べるから平気…そんな思いから焦ってフードを替えていませんか?それすら知らない・知っていてもめんどくさい・うちは大丈夫ということであれば、それまでですが…。
同じ主原料のフード(A社のチキン系からB社のチキン系のフードへ切り替える)であっても、過去に食べていたものに戻す場合であっても、少なからず、1週間から10日は様子を見ながら切り替えていくようにしましょう。
失敗例②愛犬の口のサイズに合わない大きさの粒のサイズのフードを給餌

成分や原材料などが気に入って購入したドッグフードが、愛犬の口のサイズに合っていなかったというケースもあります。結果、愛犬が食べなかったり(食べられなかったり)、早食いして喉に詰まらせてしまったり、消化がうまくいなかくて便の状態が悪くなったり…。
フードの粒のサイズはもちろん、形なども本当に色んなものがあります。それだけで、食べ方も食いつきも変わってくるほどです。小さい口の子が大きな粒のフードを食べたら、喉に詰まらせる危険もありますし、ゆっくり食べても、すぐに満腹になってしまう危険もあります。(咀嚼に疲れてしまい、栄養が足りていない状況)
逆に、大型犬の子が小型犬向けの小粒のフードを食べていると、勢いよく口にしてしまい、誤嚥してしまう危険もあり、そのくらい粒のサイズや形も馬鹿にできないんですよね。フードを替える時には、しっかり粒のサイズも気に留めておきましょう。

そんなところ見てなかった!!
粒のサイズが大きすぎる場合であれば、フードクラッシャーで砕くのもありですが、手間ですし、できればそのまま食べられるにこしたことはありません。手間を気にしないかたであれば、とりあえず、砕きさえすれば粒のサイズなんて関係なくなるのですが。
「小型犬でもちゃんと噛んで食べるので、粒のサイズは気にしなくても良い」といっている獣医もいるようですが、お伝えしたように、小さいお口で一生懸命食べることで、食べ疲れたり、満腹中枢が刺激されて、量を食べたがらなくなったりなる子も実際にいます。獣医の考えも千差万別ですから、ご注意ください。
粒のサイズについて話していくと、限られたフードの選択肢になってしまう犬種もいるかもしれませんが、フードの形や大きさなどの食べやすさみついても、フードを選ぶ時に気にかけてみてみましょう。
失敗例③闇雲にフードの評価サイトやクチコミ評判のいいフードに替える
私もかつてあったことです。という前提で、自分へ戒め(教訓)の意味も込めて、犬の飼い主として、皆さんもおそらく経験があるであろう話をします。
犬を飼っている方と自然と知り合いになって、一緒にお散歩をしたり、お話をしたりする機会ってありませんか?私のケースですが、色んな犬トークをしている時の何気ない会話から、

ドッグフード何食べてるの~?

うちは○○だよ~すごいよくって~
みたいな会話をしたことがあります。当時は犬の栄養学やドッグフードのことを全然知らなかったので、犬を飼い慣れていらっしゃる方のその話を真に受けて取り入れたり、求めていないしつけの方法を教えられたりしたこともありました。
そういった犬友トークをあてにしてみたり、フードのこともわからないので、アフィリエイト収入目的の中身のないサイトの情報を鵜呑みにしたり、わからないなりに、ネットのレビュー・クチコミを参考にしたり…。こういうの、皆さんも往々にしてやりがちなことではないでしょうか?
でも…よく考えてください。もしかしたら、相手が本当に犬のことを勉強した人かもしれませんが、9割がた…

お相手は素人さんです
良かれと思って言ってくれていたとしても、あなたの愛犬のことを相手はどれだけわかっているのでしょう?症状を聞いて正しく理解して、日常の暮らし方、口にするもの、体質などまでわかってくれるお相手ですか?お相手は犬や栄養・食に詳しい人なのでしょうか。(獣医ですらマチマチですし)
相手は自分なりに得た情報を善意で言っていたとしても、それを鵜吞みにするのか、自分でちゃんと調べて、愛犬に採用するのかの判断は飼い主さん次第です。知識のない人から聞いたことや、誰が書いたかもわからないレビューが本当に愛犬に合うのでしょうか?
クチコミだろうが、長年犬を飼っているベテランだろうが、その意見が本当にあなたの大事な愛犬に良いとは限りません。そんな人の意見やクチコミをあてにして、大事な愛犬の体質に合わないものを与えてしまわないようにしましょう。
失敗例④「なんとなくよさそう」な情報で選び、あわや体調不良に!

先ほどの話の延長的に、クチコミなどの評判がいいと「人気なんだな」「良いものなんだろうか~」と感じるのはわかります。クチコミはあてにしないでとお伝えしましたが、逆に、よくないクチコミが多いのは、それなりに悪い評価をされるなにかがあるのかもしれませんし。
悪い評価があまりに多いと、たしかにちょっと嫌ですもんね。いくら情報に振り回されないでといっていても、私もネガティブな内容が多いのは、少し心配にはなりますし…。
ただし、詳しい理由や根拠を理解していない状況で、〇〇だからよさそうという考えは危険です。
これ、よく考えてみると、愛犬の体質に合わせて良し悪しを判断している発想ではありません。言葉の響きやニュアンスから、飼い主さんがそう判断しているだけです。

よさそう=愛犬にも良いではない
なによりも大事なのは、よさそうというざっくりとしたイメージではなく、愛犬の体質に合うかどうかです。
薬膳や漢方などは自然派で良いもののように感じますが、合わない子もいます。無添加と書いてあっても、日本の無添加の表記のルールは穴だらけで、「これ入ってても無添加って名乗れるのね?」なんてことも多々あるんです。
獣医師推奨でも…契約上で推奨しているケースもあります。そういったことをちゃんと理解して、本当に愛犬に合うのか・愛犬に良いものなのか、考えた上で与えていなかったがために、アレルギー症状が悪化することもあるのです。十分注意してあげましょう。
失敗例⑤フードローテーションの意味を間違えて、愛犬に不調が!?

「フードローテーション」ってご存知でしょうか?一定期間ごとに、愛犬に与えるフードを替えていくことを言い、色んなものを食べることで、バランスよくさまざまな食材の栄養を摂取していけるようにすることです。(詳細は以下の記事をご確認ください。)
そういったローテーションの良い面だけをなんとなく知っていても、間違えたやり方でローテーションをしていては、愛犬の体に負担がかかるだけで、かえって可哀想な目に遭わせてしまう危険があります。
たとえば、アレルギー体質な子の場合。飼い主さんが愛犬のアレルギー症状に気づいておらず、ローテーションをすることで、愛犬にアレルギーが出るものを食べさせてしまう可能性はありませんか?

体にいいから食べさせたかっただけなのに…
ほかにも、あまりにショートスパンでフードを替えてしまっていたら、愛犬がグルメ化したり、胃腸に負担をかけたりする危険があります。特に食いつきが悪い・フードをえり好みするなどの理由から、すでにフードをとっかえひっかえしているのであれば、注意が必要です。
また、フードが体にフィットする前にまた新しいフードに替わることで、ただただ胃腸の調子が安定しないだけになる危険もあります。
食物アレルギーやその他の不調がないのであれば、犬は色んなものを食べた方がいいという考えは間違いではありません。しかし、フードローテーションは簡単にうまくいく子もいれば、そうはいかない子もいるので、愛犬の変化を注視しながらにしてください。
失敗例⑥「総合栄養食」と「療法食」の意味をわからないで切り替えた!
動物病院で無料サンプルが配られていたり、インターネットで気軽に買えたりしてしまう「療法食」。そもそも療法食とは、疾患や不調がある犬用の治療のための食事・食事療法のためのフードです。中身は違いますが、簡単に言えばお薬といいましょうか。
不調を治すために、一般的な健康な子が食べるドッグフードとは、栄養成分を変えて作られているため、逆にいえば、健康な子が食べるものではありません。獣医の指示ありきで、治療の一環として食べるものです。
パッケージや商品説明を見て「総合栄養食」という記載ではなく、「療法食」という記載があるものは、本来は、獣医の指示なしに一般の人が購入すべきものではありません。
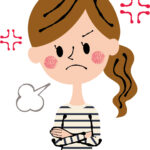
ネットで買えることも危ないけど…
個人的には、説明もなく、動物病院で療法食のサンプルをばらまく(ご自由にお持ちください的な)のも考えものじゃない?と思いますし、転売やインターネットのショッピングサイトでも診断なしに買えるのもどうかと思いますが…。
「誰でも普通に買える=与えて良いもの」と思う方がいてもおかしくありません。しかし、お伝えしているように、本来は個人判断で与えるべきではなく、獣医の指導の上で、治療として食べるものです。
最近は、療法食の取り扱いを厳しくするメーカーも増えましたが、まだまだ獣医の指導なく買える療法食はたくさんあります。療法食と総合栄養食の違いをわからずに、誤ったフードを食べさせないようにしたいのですが、私がどうこうできることでもなく…正しい認識が広がるよう啓発するしかありません。
失敗例⑦「食べないから」と、とっかえひっかえフードを替えるのはNG

食べないから・食いつきが良くないからという理由で、ドッグフードを取っ替え引っ替えしていませんか?その場合は、フードの切り替えに失敗しているのではなく、犬がわがままをしているだけです。そして、それを助長させているのは、飼い主さんご自身かもしれません。
そもそも、フードを食べなかったとしても、それってフードのせいなんでしょうか?フードが悪いのではなくて、食べない犬に何か理由がある、もしくは飼い主さんの対応のせいで食べないのかも?ということも考えましょう。まずはなぜ食べないのか?です。

うちの子何を食べてもすぐ飽きるから…

どんな子でも食べるフードが知りたい…
なんて話を聞きますが、そもそも健康な子であればフードを何日も食べないということはありません。健康に問題はないのに食べないのは、それなりに理由があるはずです。
それを考えないで、食べないからとフードをあれこれ替えていたら、犬はどんどんグルメ化していき、「もっと美味しいもの出さないと食べない」という態度を取ります。フードの切り替えの失敗ではなく、飼い主さんにも責任があることを考えておかなければなりません。
失敗例⑧変更前と後のそれぞれのフードのカロリーの違いを意識して !
「うちの子は、1日に◯g食べます」と、グラムで愛犬のごはんの量を把握している方、要注意です!
本来は、何グラム食べるかではなく、1日になんカロリー摂取しなければならないかが重要で、考えておきたいのはグラム数ではありません。
例として、以下のようなわんちゃん・切り替えるフードという前提で考えてみます。
- 元気な10kgの成犬(去勢済)体型は標準
- 運動量も多すぎず少なすぎず適度な量
- 切り替える前の現行のフードA:368kcal/100g
- 新しく切り替えるフードB:340kcal/100g
まず、10kgの去勢済の成犬の子が1日に必要なカロリー数を計算しますと、629.8calです。(計算方法はこちらの記事に記載してありますのでご確認お願い致します。)

しっかり計算して与えていますか?!
Aのフードの場合だと、171.14g食べていれば必要なカロリー数は摂取できます。(おやつを食べる子であれば、もちろん、給餌量も調整が必要です)しかし、Bのフードの場合であれば、185.24g食べていないと必要なカロリーが摂取できません。
たかが数グラムと思うかもしれませんが、犬からしたらその数グラムですら全然違うんです。そのちょっとの過不足で、体にも大きく影響があります。もし、フードを替えてから愛犬が太った・痩せたと感じたのであれば、給餌量を間違えていないか確認してみましょう。
フードのパッケージに記載されている給餌量は、あくまで目安に過ぎません。どんなフードを与える時でも動じないでいられるよう、正しく計算できるようにしておけるといいですね。
失敗例⑨ライフステージや生活に合っていないものに替えて愛犬に不調が…

体重管理フード、パピー用フード、シニア用フード、お腹の調子が悪い子用など、それぞれの犬の状況に合わせて与えられるように作られているフードがありますが、そういったフードに切り替えている場合は注意が必要です。
など、なんらかの思いや理由があるのかもしれないにせよ、犬の体調・年齢・運動量に見合わないフードに切り替えてしまったことで、目先のことはよくても、あとあと、愛犬の体に不調をきたす原因になってしまうことがあります。
仮に、必要カロリーの給餌量があっているのに、太った・痩せたという場合は、たんぱく質含有量や脂質量などの栄養成分が、愛犬の生活に見合っていないからです。

思いこみで対処するのは危険
食べる量が少ない・太らせたいなどの場合、パピー用の普通より栄養が高い(高脂質)のものを与えたら、たしかに体重もキープでき痩せることは回避できるでしょうが、皮下脂肪がついて、不健康な体重の増え方をしただけにすぎません。
筋肉をつけようと高たんぱくフードを与えても、運動量に見合っていなければ、筋肉はある程度ついたとしても、余分な栄養が脂肪に変わり太るだけです。だからって、給餌量を減らして体重をキープしたところで、ビタミン・ミネラルのバランスも崩れ、健康を害する危険があります。
フードを替える時は、フードそのもののカロリーはもちろんですが、成分も愛犬の体質や生活スタイル・年齢に見合うものを選べるようにしておきたいですね。
フードの切り替えはゆっくり時間をかけて!失敗したらどうなる?

ドッグフードの切り替えに失敗したら、
- 太った、痩せた(想定外の体重の変化)
- お腹を壊した(軟便、便秘、下痢、おならなど)
- 吐く、えずく、吐きだがる
- アレルギー症状が出た(カイカイ、発疹、涙やけなど)
- 食べなくなった、食いつきが悪くなった
などが起こることがあります。
どれも、愛犬の健康という意味では良いことではありせん。しかしこれらは、飼い主さんがフードを切り替える時に気を付けていれば回避できることもありますし、切り替えるフードの選び方さえ間違えなければ、回避できることもあります。
原則は、フードの切り替えは時間をかけて、愛犬の胃腸に負担のかからないようにしていくよう心がけましょう。なお、本当に体質に合わなくて不調が出てしまっているケースもありますので、心配な場合は必ず獣医に相談してみてくださいね。