愛犬に野菜やフルーツ、加熱した肉や魚を与えたことはありますか?もちろん、与えるにしても犬が食べても大丈夫か・犬も食べられる食材かということを、インターネットで調べたうえでだと思います。
しかし、ネットに掲載されている情報は、「中毒を起こすようなものが入っていないから、犬も食べても大丈夫」「犬が食べてはいけないものではない」というだけであって、与えた方がいいともは言っていませんし、むしろ与えない方が良いものもあるものです。
「この食材を取ったらこんな栄養が摂取できるよ」「こんな作用が期待できますよ」なんて説明も記載されていますが、与え方を間違えるとそれがデメリットになり、愛犬の健康を害する危険もあります。

その食材の栄養とか説明してあるけど、注意点もたくさん!!
与えても大丈夫でも、与えない方がいい食材はたくさんありますし、量や回数、与え方に注意しないといけないこともあり、原則、ドッグフード(総合栄養食)を食べられる子であれば、野菜やフルーツ、おやつは不要です。
それに、私自身は「おやつは絶対やめて!」とは思っていません。ただ、与え過ぎてしまう・間違えた与え方をしてしまう飼い主さんは多いです。そこで今回は与えても良いとはいえ、犬の管理栄養士がそんなに与えない野菜やフルーツをピックアップしました。
なお、いろいろ書いてありますが、犬の体質には個体差がありますので、「うちの子に合う方法を聞きたい・相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。(状況によっては、動物病院へ行くことをおすすめすることもあります。※相談・サポートは有料です。)
(※お問い合わせについて:当サイトからのメールが迷惑メールに振り分けられることがあるので、迷惑メールボックスもご確認ください)
与えても大丈夫とはいえ、与える量・回数は控えた方が良い食べ物
インターネットで調べて犬が食べても良いと紹介されている食材もあれば、玉ねぎやぶどうのように中毒を起こし、命の危険がある食材などもあります。
ただ、食べても良いとされている食材であっても、量や与え方、与える頻度に注意しておかないといけない食材もたくさんあることを把握できているでしょうか?
ここからは、犬の食いつきもよく、

この野菜(フルーツ)うちの子大好きなんだよね!
というケースも多いであろう、犬に人気な食材でもありながらも、
- 与え過ぎると危険な食材
- 犬の管理栄養士がおやつやトッピングとして与える量に注意している食材
などを、まとめてご紹介していきます。参考になれば幸いです。
※なお、以降ご紹介する食材の成分は、文部科学省が提示している、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとにしています。
与えても良いとはいえ、量は控えた方が良い食べ物①サツマイモ

さつまいもを嫌いなわんこなんている?!と思うほど、さつまいもって犬に大人気な食材ですよね。実際、ドッグフードにも配合されていることも多々ありますし、犬のおやつ売り場でも、サツマイモのおやつはたくさん販売されています。
しかし、あくまでそれは、メーカーがフードとして成分を把握して使用されているものであって、ご自宅でおやつやトッピングとして与えるのとはわけが違うのです。なんグラム与えて、どのくらいの栄養成分が犬の体内に入るのかわかっていないのであれば、量は控えたほうがベター。
まず、特筆すべきサツマイモの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部・皮なし・茹でた状態の数値です)
| カロリー | ビタミンC | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 131kcal | 29mg | 480mg | 2.3g | 29.6g |

カロリーも糖質もたっか!!
「サツマイモは食物繊維が豊富でお腹の調子を整える」って聞いたことありませんか?しかし、食物繊維が多すぎると、逆に超を傷つけてしまうことがあります。これではかえって胃腸の負担になるだけです。食物繊維は多く取ればいいという話ではありません。
繊維が有効に働くには有用菌(腸内の健康を保つ働きをする善玉菌・乳酸菌やビフィズス菌など)が必要です。食物繊維は有用菌のエサになる成分で、食物繊維が体内に入ってきて、有用菌がその食物繊維を食べます。結果、善玉菌を増やして腸内環境を安定させる仕組みにです。
つまり、もし、愛犬のお腹に有用菌が足りていなかったり、定着していなかったり、そもそも有用菌バランスが崩れていたり、悪さをする菌がいたりするようであれば、食物繊維をたくさん食べたところで、効果がありません。

繊維を取る=お腹が安定するわけではない!
また、ビタミンCは、健康な犬であればわざわざ摂取させる必要はなく、体内で生成することができる成分です。胃腸が弱い子や、投薬中の子の場合、ビタミンCの酸味で余計に胃腸が荒れてしまうことがあります。
カリウムは、余分な水分を体外に出して、血圧などを安定させる作用があるとはいえ、多いければいいというわけではありません。心臓、腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。
なにより糖質の高さがかなりネックです。血液がドロドロになり太る原因になることがあります。糖化しやすくないもの=炭水化物(糖質)が低いものかどうかを見ておかないといけません。糖質が高いものは、肥満リスクと腎臓に負担をかける要素ですので、ご注意ください。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物②カボチャ

カボチャもドッグフードに配合されていることも多く、おやつなどでも使用されることのある野菜です。もちろん、犬も食べることができます。しかし、カボチャも与え過ぎないようにしておきたい野菜です、
まず、特筆すべきカボチャの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です。今回は西洋系のカボチャではなく、日本の品種での数値を採用します。)
| カロリー | βカロテン | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 55kcal | 1100μg | 350mg | 3.0g | 10.3g |

βカロテンはカボチャのオレンジ色の色素成分
βカロテンは体内でビタミンAに変換されるのですが、ふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけますし、運動量や年齢などによっては、摂取しすぎることでビタミンA中毒を引きを起こし、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあるので注意が必要です。
そして、さつまいもと同じくカリウムが多いですが、カリウムは余分な水分を体外に出して、血圧などを安定させる作用があるとはいえ、多いければいいというわけではありません。心臓、腎臓の持病や、犬種特有の注意しておきたいことがある場合、摂取量を制限する必要があります。
さらに、炭水化物(食物繊維+糖質)も高いですが、肥満や肝機能数値の異常の原因にもなり兼ねませんし、繊維の多さから軟便になる可能性も否めません。繊維が多ければ良いという考えは間違いです。愛犬に合うかどうか、しっかり考えて与えるようにしましょう。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物③リンゴ

リンゴを使ったおやつも販売されていますし、人間からすると、「りんご一個で医者いらず」なんていわれることもあるほど、高栄養価で優秀な食べ物ですよね。もちろん、犬にも良い効果はあるので、適量・小さく刻んでなら与えてもかまいません。
しかし、いくら体に良いとはいえ、やはり取り過ぎたり与え方を間違えたりすると、愛犬の健康を害する危険があります。与え方には注意が必要ですので、「りんご=体にいい」と率先して与え過ぎないようにしてください。
まず、特筆すべきリンゴの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | カリウム | ソルビトール | 食物繊維 | 糖質 |
| 53kcal | 120mg | 0.7g | 1.4g | 12.7g |

カロリーも低いしよさそうだね
さつまいもほど糖質も高くなく、コレステロールもゼロなのですが、それでも犬にとっては結構な糖質量にはなりますし、一番の問題は糖アルコールの一種であるソルビトールがあり、少量であれば害はないとはいわれているものの、過剰摂取でお腹を壊す危険があること。
ほか、りんごには抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれているなんていいますが、それはりんごの皮の部分に多く含まれています。犬に与える場合には皮は剥いて与える方がいいため、犬にとっては、りんごのポリフェノールがどうのは意味がない話です。
さらに、硬い食べ物ですので小さく切って与えてあげないと、消化器官の負担になってしまいます。噛み切れないサイズの果実を与えている方がいますが、犬は噛まずに飲み込んで食べる生き物です。飲み込んでも問題ないサイズにして与えましょう。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物④バナナ

小腹を満たすのみちょうどいいバナナ!ドッグフードにも犬のおやつにも配合されていることもありますし、高栄養価なのでフードメーカーからしたら、重宝する食材だと思います。
しかし、フードに配合しているのと、飼い主さんが別途おやつやトッピングとしてバナナを与えるのは別のお話です。案外、バナナって扱いが難しい食べ物なので、与える量には注意しなければなりません。
まず、特筆すべきバナナの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | βカロテン | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 93kcal | 42.0μg | 360mg | 1.1g | 21.4g |

わぁ…糖質がとっても多いね…
バナナを食べると食物繊維がとれでお通じがよくなるといわれていますが、これはサツマイモのところでご紹介したとおり、食物繊維が多すぎると、逆に超を傷つけてしまうことがあります。これではかえって胃腸の負担になるだけです。
さらに、ただ食物繊維は多く取ればいいという話ではありません。繊維が有効に働くには有用菌(腸内の健康を保つ働きをする善玉菌・乳酸菌やビフィズス菌など)が必要です。食物繊維は有用菌のエサになる成分で、食物繊維が体内に入ってきて、有用菌がその食物繊維を食べます。
そうすることで、さらに善玉菌を増やして腸内環境を安定させる仕組みにです。つまり、もし、愛犬のお腹に有用菌が足りていなかったり、定着していなかったり、あるいは悪さをする菌がたくさんいたりするようであれば、食物繊維をたくさん食べたところで効果がありません。

それよりも、糖質の高さゆえに太りそう…
また、βカロテンは体内でビタミンAに変換されるのですが、ふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけますし、運動量や年齢などによっては、摂取しすぎることでビタミンA中毒を引きを起こし、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあるんです。
カリウムも利尿作用やほてりを取るなんて言われますが、カリウムが多いのはいいことばかりではなく、心臓・腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。
このように、フードに配合されている場合は、フード製造のプロが、トータルバランスをみてバナナの有効な成分を生かして配合しているのであって、別途、飼い主さんが与えるのとは全く異なるので、いった食材をおやつを与え過ぎないように気をつけてください。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物⑤桃

甘みがあって、ジューシーな桃!食べた後に、その水分の多さから、手がべちゃくちゃになってしまうこともありますよね。香りもよく、犬も食べることはできますが、与えない方がいい場合もあるので、注意してください。
まず、特筆すべき桃(白桃)の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 38kcal | 88.7g | 180mg | 1.3g | 8.9g |

90%近くが水分ですね
その水分の多さゆえに、お腹を壊してしまう子もいます。そして、糖質もそこそこある方です。ただでさえ、桃は糖質がある果物なのですが、缶詰はあまーいシロップにどっぷり漬けられ、とんでもない糖質量になるので、与えないようにしてください。
また、意外にも桃はバラ科に属するフルーツなのですが、バラ科の食べ物(りんごやさくらんぼ)には、食べると喉や口などがイガイガ・チクチクする成分が含まれています。そういったアレルギーが出ていないか注意しなければなりません。
さらに、種の内側には枇杷や青梅などにも含まれる「アミグダリン」という毒性のある成分が含まれています。誤食させないように注意してください。こんなに注意したポイントがある桃ですから、わざわざ与えないという選択肢を飼い主さんが持っていられると良いですね。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物⑥マンゴー

南国の印象が強い、パッションフルーツ!最近では国産のマンゴーも定着しはじめています。犬も食べることができるのですが、筋があるような感じもあり、繊維が多い気もしますが、実際はどうなんでしょう?
まず、特筆すべきマンゴーの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | βカロテン | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 68kcal | 610μg | 170mg | 1.3g | 15.6g |
βカロテンは体内で、ビタミンAに変換されるのですが、ふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけますし、摂取しすぎることでビタミンA中毒を引きを起こし、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあるので注意が必要です。

結局、摂取しすぎるのはよくない
カリウムについても、余分な水分を体外に出して、血圧などを安定させる作用があるとはいえ、多いければいいというわけではなく、心臓・腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。
ほかにも、ドライマンゴーは糖質も高いので与えないに越したことはありませんし、繊維も多いほうな果物ですので、もともとお腹が不安定気味な子にのっては消化の負担になる可能性も否めません。
なお、マンゴーはウルシ科の食べ物で、皮の成分で皮膚炎の原因になることもあるので、皮の付近を犬に食べさせてしまったり、犬が届くところに置いておいたりしないように注意してください。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物⑦柿

秋のフルーツの代表のひとつでもある柿。住んでいる環境にもよりますが、ご自宅のお庭で収穫できるという人もいたり、ご近所さんにもらえたりするようなかたもいるかもしれません。
まず、スーパーなので買うような柿であれば、犬に与えることは可能ですが、おすそ分けでもらったような柿で、まだしっかり熟れていないようなものや、渋柿は注意が必要です。しかし、スーパーで買ったようなものであっても、注意したいポイントはあります。
まず、特筆すべき柿の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | β−クリプトキサンチン | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 63kcal | 500μg | 170mg | 1.6g | 14.3g |

結構、糖質高いのね…
干し柿にしたとき白くなるのは、柿に糖質がふんだんにあるからなんですね。ふつうに食べると、そんなに感じないかもしれませんが、柿にはそれなりに糖分があるため、たくさん食べないようにしなければなりません。干し柿も食べても良いとは言え、与えない方がよいでしょう。
また、β−クリプトキサンチンは、オレンジ色の食品に含まれる天然色素で、カロテノイドの一種です。体内でビタミンAに変換され、酸化作用を発揮して健康にいい効果があるともされていますが、しかし、ビタミンAはふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけます。

でもね、犬も甘いもの(糖質)は好きなんだよね
たくさん食べさせたら、肝臓などに負担をかけることもありますので、やはりこれも、いくら良い作用が期待できるとはいえ、わざわざせっせと愛犬に摂取させる必要はありません。
基本的に、犬も甘いものは大好きではありますが、市販の犬用おやつ(ビスケットやケーキなど)よりもフルーツならいいだろうと油断して与えている方もいるかもしれませんが、フルーツは本当に思った以上に糖質が高いものが多いんですよね。
繊維も多くカリウムも多く、お腹が弱い子にとっては与えない方が良い側面もあります。ほかにも熟れていない柿や渋柿にはアルカロイドという有害物質も含まれていますし、トータルで考えたら、適正量のみ食べさせたとしても、そんなに与える必要はないといえるでしょう。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物⑧いちご

いちごはフルーツの中でも、比較的低カロリーで、糖質もほかのフルーツや野菜よりも低いため、与えやすいものには該当します。実際に、おやつなどにもイチゴを配合したものもあるくらいなので、食べてはいけないということはありません。
しかし、糖質やカロリーという意味以外で、少し注意したいこともあります。まず、特筆すべき苺の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | 葉酸 | ビタミンC |
| 31kcal | 90.0g | 10mg | 90μg | 62mg |

少量であれば食べさせても大丈夫
いちごの90%が水分ということもあり、水分をあまりとってくれない・取れない状態であれば、イチゴを与えるメリットはあるのですが、基本的には、総合栄養食(ドッグフード)を食べて、水分もそれなりに摂取している子であれば、特に率先して与える必要はありません。
それに、ビタミンCは体内で生成することができる成分です。ビタミンCは、健康な犬であればわざわざ摂取させる必要はありませんし、胃腸が弱い子や、投薬中の子の場合、ビタミンCの酸味で余計に胃腸が荒れてしまうことがあります。お腹を壊しやすい子にはおすすめはしません。
さらに、イチゴには微量ですが、天然のキシリトールが含まれていています。少量たべるくらいであれば問題はないとはいわれていますが、キシリトールが苦手な生き物である犬に、わざわざ与えなくてもいいですし、与えてもごく少量でいいのではないでしょうか。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物⑨栗

甘くてほくほくな栗も、一部ドッグフードで配合しているものもあります。もちろん、犬が食べてもいいのですが、注意したいポイントがこれまで紹介した野菜・果物よりも多いかもしれません。
まず、特筆すべき栗の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | リン | カリウム | 食物繊維 | 糖質 |
| 207kcal | 110mg | 560mg | 8.5g | 40.0g |

カロリーも糖質もめちゃ高!!
まず、殻付きのまま・皮付きのまま与える人はそんなにいないでしょうが、皮や殻は消化に悪いので与えるべきではありません。しっかり加熱して、殻・皮をむいて与えましょう。しかし、与えたとて、とにかく栄養が高いので、与え過ぎると肥満の原因にもなりかねません。
シニア期になってきてあまり食べなくて、栄養が全然とれていないなどでもないのであれば、栗のカロリーと糖質の多さは考え物です。
また、リンの多さも非常に注意が必要で、AAFCOの基準にも、犬が食べものから摂取するのリンとカルシウムの比率は、1:1~1:2が適切とされており、このカルシウムとリンのバランスが壊れると腎機能に負担をかけることにもつながります。

甘くてホクホクだからたくさん食べたいんだけど…
リンの過剰摂取は、腎臓のみならず、腎臓に関係する尿路のトラブルにも派生してしまうため、良いことはひとつもありません。
そもそも一般的に販売されている総合栄養食(ドッグフード)を食べていたら、このリンとカルシウムの1:1~1:2のバランスはクリアしている状態になっているので、それさえ食べていれば、わざわざリンの高い食べ物なんて与えなくていいのです。
実はこのバランスは、手作りフードで管理するのは非常に難しいともいわれています。無知なまま、「健康によさそう」「フードジプシーには手作りフードしかない」と、安易に手作りフードに手を出すと、生涯背負う健康トラブルに発展しかねませんので、重々注意してください。
与えても大丈夫とはいえ、量は控えた方が良い食べ物⑩ほうれん草

日本の食卓にもよく並ぶほうれん草。サラダなんかにも使用されることもあり、和洋問わず、使い勝手のいい食材ですし、実際に、ドッグフードにも配合されていることもありますよね。もちろん、犬も食べても大丈夫なのですが、与える量には注意が必要です。
ほうれん草に多く含まれるシュウ酸カリウムは結石の原因になりやすいなんて聞いたことありませんか?これ、人間だけでなく、犬にとっても言えることなんです。尿路トラブルに陥りやすい犬種を飼われている方は注意してください。
まず、特筆すべきほうれん草の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | βカロテン | ビタミンK |
| 23kcal | 91.5g | 490mg | 5400μg | 320μg |
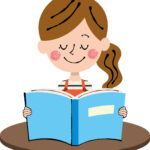
意外にも水分が多いんですねぇ
ふだんの食生活で、野菜の水分含有量とかってそこまで気にしてないかたも多いとは思いますが、実は、ほうれん草って結構な水分含有量なんですよね。水分の多いものは、お腹をこわしかねないので、お腹が弱い子は与えない方がよいでしょう。
そして、止血作用などもあるビタミンKも多いのですが、犬は腸内細菌によって合成してビタミンKを作り出すことができるので、ふだんドッグフードを食べてい犬であれば欠乏することもありません。つまり積極的に取らなくても良い成分です。(※過剰摂取しても悪い影響はありません)
βカロテンは体内でビタミンAに変換されるのですが、ふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけます。運動量や年齢などによっては、摂取しすぎることでビタミンA中毒を引きを起こし、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあるんです。

ちゃんとわかってないと痛い目に遭うのは愛犬なんだよ
カリウムも、利尿作用やほてりを取るなんて言われますが、カリウムが多いのはいいことばかりではなく、心臓、腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。
腎臓・尿路系のトラブルがある子にはカリウムの摂取量は控えた方が良いので、与える必要はありません。しかるべく、量を調整されている療法食を食べていたら良いので、トッピングやおやつでも油断はしないようにしてください。
犬にドッグフード、プラスαでなにかを与えるということは、本来、トータルの栄養バランスを考えて作られているものを食べているにも関わらず、飼い主さんが勝手に追加で与えているだけに過ぎません。トッピングやおやつが原因で、愛犬の健康を害することもあるのです。
ネットの情報は危険が多い!飼い主さんが正しい見る目を養おう!

この仕事をしてから、「〇〇は犬にも良いって聞いたから与えるようにしているんです」「△△は犬に与えちゃダメって聞いた」など、ほーーーーーーんとうに、ごめんなさいですが、その言ってた人がどんな人なんだろうと思うような、

誰から聞いたんそれ…?
と言いたくなるようなことにたくさん遭遇します。栄養のことをわかっていない人のアドバイスは真に受けず、信ぴょう性を吟味して、飼い主さんがしっかり情報を選択しなければなりません。
ほかにも、
などという、犬が食べても良いものという事実だけを切り取って、与えるデメリットを理解しないままたくさん与えてしまっている方も多いです。

ネットじゃなくて、僕を見てください!!
犬という生命体自体が絶対に受け付けない(食べたら不調を起こす)、玉ねぎやチョコレート、ぶどうなどの食べ物はもちろんありますが、中毒性のないもので食べられるものについては、何が良い・悪いというのは、その子の体質によって違います。
こういう子なら〇〇はいいよ、こういう症状の子には△△はやめた方がいいよ、など判断が違うのですから、犬に与えても良いというものであっても、ドッグフード以外のものについては、しっかり情報を選んぶようにしてください。
愛犬との食生活を、コミュニケーションとして楽しむのはとても素晴らしいと思いますが、良いものだろうとやっていたことが、実際は、愛犬の健康を害していた…。そう気づいてからでは遅いです。重々注意してくださいね。


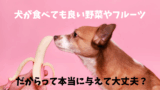
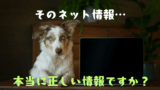
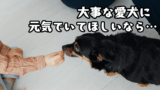


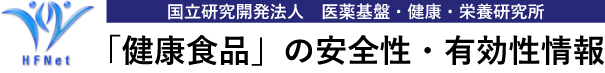


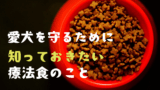
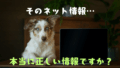
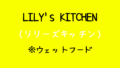
コメント