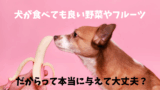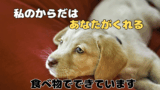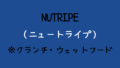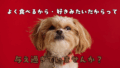インターネット上に「犬が食べても良いフルーツ」「犬が食べても良い野菜」なんて記事があふれています。しかし、与えても良い・食べても大丈夫というだけであって、与えたほうがいいという書き方はしていないのではないでしょうか?
人間が食べるものを愛犬がおいしそうに食べている姿を見ると、与えた側も嬉しくなって、エスカレートして与えたくなることもあると思います。それに、良い栄養があるものもありますから、絶対に与えないほうがいいというわけでもありません。

おいしそうに食べる姿って可愛いじゃん
しかし、実際は、たとえ犬も食べることができて、プラスアルファの栄養がとれるメリットもあったとしても、それ以上のデメリットがある食材もあるものです。そこで今回は、犬の管理栄養士の私が、愛犬に与えない野菜やフルーツなどをご紹介します。
なお、いろいろ書いてありますが、犬の体質には個体差がありますので、うちの子に合う方法を相談したいという方は、お気軽にお問い合わせください。状況によっては、動物病院へ行くことをおすすめすることもあります。(※相談・サポートは有料です。)
(※お問い合わせについて:当サイトからのメールが迷惑メールに振り分けられることがあるので、迷惑メールボックスもご確認ください)
食べても大丈夫…でも犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの

まずはじめに、一番伝えたいのは、ドッグフードを問題なく食べている子であれば、おやつや野菜やフルーツ、トッピングは本来は不要です。それが大前提なのですが、みなさん、「このフルーツ(or野菜)って犬にも与えて良いのかな?」と、調べたことはありませんか?
ネット記事では、食べても良いのかダメなのか、どんな成分が摂取でき、どのくらい与えていいのかなどをはじめ、注意したい成分やデメリットも説明はしているものの、残念ながら、デメリットを正しく把握しいる飼い主さんは少ないです。
デメリットを記載していないネット記事は論外ですが、たとえデメリットが書いてあったとしても、犬にとって良くない成分が入っていないから、食べられるといっているだけであって、食べることが良いということではありません。かなり無責任な発信、やめてほしいです…。

デメリットはしっかり見ておくべきです
人間は、必要な情報を知れたら他の情報を雑音と感じ、ものごとを見たいようにみます。記事を出しているサイト側も、その人間の傾向・習性をわかった書き方をしており、結果、デメリットをしっかり伝えらていません。このような状況から、
- 調べたら、食べても良いと書いていたから大丈夫だと思っていた×
- こういう成分が豊富って書いてあったから良いものだと思ってた×
- この食材にはこういう栄養があると書いてあったので良かれと思って…×
と、愛犬の健康を害する恐れのある食材・体質に合わない食材を与えている飼い主が多発しています。あなたが愛犬に与えた食べ物が原因で、愛犬の健康を害してしまって後悔したくないのであれば、一時的な幸せのために愛犬の健康を損ねないよう、一緒に学んでいきましょう。
なお、このお話は、市販のドッグフードにおける原材料としての配合に対してではなく、あくまでご家庭でおやつとしてフード以外に与える食材についての話です。この原材料が配合されているフードはダメという話ではありませんので、誤解なきよう。
※ご紹介する食材の成分は、文部科学省が提示している、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとにしています。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの①すいか

暑い夏の風物詩・スイカ。低カロリーだから・良い成分があるからと、たくさん与えていないでしょうか?まずはじめに、特筆すべきスイカの成分をご紹介します。(以下の数値は、赤玉・100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | βカロテン | 炭水化物 |
| 172kcal | 89.6g | 120㎎ | 830μg | 9.5g |
水分量が多く、スイカを食べることで水分摂取できるだの、解熱作用があるだの言われるものの、意外にも炭水化物(糖質)も高く、与え方に注意しなければなりません。その水分量ゆえにお腹の不調の原因になることもあります。
また、糖質の多さから、食べ過ぎることで血液がドロドロになり太る原因になることがあります。炭水化物が多い食材の場合は、カロリー・脂質量だけで判断するのではなく、糖化しやすくないもの=炭水化物(糖質)が低いものかどうかを見ておかないといけません。

食べてもいいからって与えるの、やめませんか?
また、カリウムには、余分な水分を体外に出して、血圧などを安定させる作用があるとはいえ、多いければいいというわけではなく、心臓、腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。
ほかにも、βカロテンは体内で、ビタミンAに変換されるのですが、ふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけますし、運動量や年齢などによっては、摂取しすぎることでビタミンA中毒を引きを起こし、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあるのです。
種を食べさせないことや、絶対ではないとはいえ、スイカアレルギーが(イネ科・ウリ科・キク科のものが合わない子に起きやすい)出る危険性があることなども考慮すると、率先して与える必要はないのではないでしょうか?アレルギーがちな子は、避けた方がいい食材です。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの②トウモロコシ

とうもろこしは、一部のドッグフード(総合栄養食・おやつ)にも使用されることもありますので、何の疑いもなく与える人もいるかもしれません。しかし、本来は与える必要はありませんし、与えるにしても注意しないといけない食材です。
まず、特筆すべきトウモロコシの成分をご紹介します。(以下の数値は、黄色種の茹でた状態の100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | カリウム | 葉酸 | 食物繊維 | 糖質 |
| 95kcal | 290㎎ | 86μg | 3.1g | 15.5g |

甘くておいしいけどアレルギーリスクもあります
トウモロコシはたんぱく質も多く、赤血球を生成する葉酸も豊富で、さらに食物繊維も糖質も豊富です。糖質も高く、瞬発的にエネルギーに変える栄養があるのですが、トウモロコシに含まれるたんぱく質は、良質なたんぱく質ではありません。バランスの悪いアミノ酸です。
さらに、糖質が高いがゆえに、太りやすく肥満や肝機能などに心配がある子には注意が必要です。また、繊維が多いとはいえ、分解しづらく、お腹の不調を起こし、アレルギーを起こしてしまう危険があります。(コーンの皮を除いたとしても同じです)
なお、コーンスターチ、コーンミールなどであっても、体質に合わない子も多いため、わざわざ率先して与える必要はないのではないでしょうか?旬の野菜をあげたいのであれば、愛犬に嫌な変化が出ないよう、頻繁には与えないなど注意しておいたほうがベターです。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの③みかん

寒くなってきた秋口から、春先までたくさんの品種がある、みかん(柑橘類全般)も、あまり率先しては与えたくないフルーツです。
まず、特筆すべきみかんの成分をご紹介します。(以下の数値は温州みかん・100gあたりの可食部の数値です)水分が多く、ビタミンCも豊富なのがわかりますよね。
| カロリー | 水分 | ビタミンC | β−クリプトキサンチン | 糖質 |
| 49kcal | 86.9g | 32mg | 1700μg | 11g |

低カロリーだし食物繊維が豊富ってよく聞くけど…
そして、食物繊維が豊富と聞いたことがあるかもしれませんが、含有量はたったの1.0g/100g。ほとんどが糖質です。しかも食物繊維が豊富なのは、みかんの白い皮や筋の部分。この部分は消化に悪いため、犬に与えるべきではありません。
与えてしまうと、お腹壊して下痢や嘔吐、腸閉塞などの消化器官トラブルに見舞われる危険があります。つまり、犬に与えるために皮や筋を取ったみかんには、食物繊維が豊富というメリットはほぼありません。
また、ビタミンCは、健康な犬であればわざわざ摂取させる必要はありません。ビタミンCは体内で生成することができる成分です。胃腸が弱い子や、投薬中の子の場合、ビタミンCの酸味で余計に胃腸が荒れてしまうことがあります。気軽にみかんなどの柑橘は与えるべきではありません。

β−クリプトキサンチンってなに?
そして、β−クリプトキサンチン。これはカロテノイドの一種で、鮮やかなオレンジ色の色素の成分です。体内に入るとビタミンAに変換されるのですが、ビタミンAはふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけます。よって、たくさん与える必要はありません。
老けないため(骨、被毛、粘膜、関節ケア成分の維持など)の抗酸化作用があるのですが、運動量や年齢などによっては、摂取過多でビタミンA中毒を引きを起こし、関節にトラブル(足の麻痺・歩行困難などが起きたり、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあります。
種を取って与えないといけない、皮や筋は取って与える、小さくして食べやすくして与えるなどの諸条件と照らし合わせても、わざわざみかんを与えるメリットはあるのでしょうか?
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの④納豆

今では黒豆の納豆や、においが少ない納豆、大粒・小粒・ひきわりなどなど…たくさんのシリーズ展開がされている国民食・納豆!(もちろん、においや粘りなど、クセの強さから苦手な人もいると思いますが)
まず、特筆すべき納豆の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたり・ひきわりなどではない全粒タイプの可食部の数値です)
| カロリー | たんぱく質 | 食物繊維 | ビタミンK | リン |
| 184kcal | 16.5g | 9.5g | 870μg | 220mg |

ほかにもナットウキナーゼも有名ですね!
大豆製品で、5大栄養素のひとつでもあるたんぱく質が豊富です。が、植物性のたんぱく質より動物性のたんぱく質の方が吸収しやすいため、動物性のたんぱく質(=肉・魚)を食べられる子であれば、わざわざ大豆製品からとる必要はありません。
まして、食べ過ぎや体質的な問題から、大豆アレルギーが出るわんこもいます。犬に納豆を食べさせるのであれば、アレルギーが出ないか、長期的に与えていっても大丈夫なのかを慎重に見極めてください。それに、ネバネバで口周りが汚れたり、菌が繫殖したりするリスクもあります。
さらに、リンは骨・歯・細胞の生成に必要な成分ですが、植物性よりも動物性の方が吸収しやすいですし、過剰摂取してしまうと腎臓の機能に負担をかけてしまいます。すでに腎臓に不調があれば、摂取制限が必要になるので注意しなければなりません。

リンとカルシウムのトータルバランスが重要です
なお、ビタミンKは、血液を固めたり、骨を形成したりする成分なのですが、ビタミンKを犬は腸内細菌によって生成できます。そのため基本的には欠落することもないため、ふだんドッグフードを食べているのであれば、プラスアルファで摂取しなくても問題ありません。
ナットウキナーゼも 高カロリー・高脂質な食生活をしている場合には有効とはいわれていますが、しかるべく正しい食生活をさせていたら、ビタミンK同様、わざわざ与える必要はありません。
人間には食べたらいい効果があるとされているものの、それを取らないといけないような不健康な生活をしているからなだけ。犬に納豆を与えないといけない状況にする前に、運動や適切なフードの見直しをしてみてはいかがでしょうか?与える必要はありません。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの⑤白米

ドッグフードにも白米は配合されていることがあり、もちろん犬が食べても問題ない食材なのですが、あくまでそれは、ドッグフードとしてトータルバランスを整えるために配合されている場合の話。おやつやトッピングとして与える必要はありません。
まず、特筆すべき白米の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | リン | たんぱく質 | 糖質 |
| 156kcal | 60.0g | 34mg | 2.5g | 35.8g |

糖質、めっちゃ高いよね?
はっきり言って、アレルギーリスクが少ないことくらいしか、メリットは特にありません。しかも、糖質の高さがかなりネックです。糖質の多さから、食べ過ぎることで血液がドロドロになり太る原因になることがあります。
炭水化物が多い食材の場合は、カロリー・脂質量だけで判断するのではなく、糖化しやすくないもの=炭水化物(糖質)が低いものかどうかを見ておかないといけません。日本人にとって主食でもある白ごはんですが、太る要素と腎臓・膵臓に負担をかける要素の宝庫のようなもの。
太って脂肪がつき、肝機能などの血液数値に異常が出たっておかしくありません。また、人間の主食だからこそ、犬には与えないほうがいいと思います。人間の食事中に、「自分(犬)も一緒に食べられる!」と勘違いさせるだけではないでしょうか。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの⑥ゆで卵

卵はドッグフードにもよく配合されていますよね。高栄養価ですし、フードを固める役割もあるので使い勝手が良いのでしょう。ちなみに、犬に生卵(卵白)は絶対にNGなので与えないようにしてください。
今回は「ゆで卵」についてですが、まず、特筆すべきゆで卵の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | コレステロール | ナトリウム | ビオチン | たんぱく質 |
| 134kcal | 380mg | 140mg | 25.0μg | 12.5g |

高たんぱく!たんぱく質は必要不可欠な成分です
お伝えしたように、大変栄養価が高い食材ではあるのですが、ドッグフードを普通に食べている上で、さらにおやつやトッピングとしてゆで卵を与えてしまうと、高栄養価すぎるあまり、栄養がオーバーしてしまい、肥満や心臓への負担になる原因になることがあります。
ナトリウム(塩)も必要な成分ですが、普通にドッグフードを食べている子であれば、問題ありません。プラスアルファで与えると摂取過剰になり、腎臓や心臓に負担をかける危険があります。なお、犬に塩はダメと勘違いしている方がいますが、犬にも塩は必要不可欠なので誤解なきよう。
また、手作りフードだと、ナトリウムが摂取しづらくなる傾向がありますので、個人で手作りフードを作りたい方は、獣医や栄養のプロに確認しておこなうようにしましょう。個人判断で簡単にできることではありません。(ネットで調べたレシピもおすすめはしません。)

ナトリウム(=塩)は摂取量に注意が必要というだけの話
つまり、ふだんから健康的にフードを食べている子であれば、ゆで卵なんて与えていたらナトリウムの過剰摂取になるので、与えない方が良いと思いますよ。
そして、人間でもよく言われることなのでご存知の方もいるでしょうが、卵はコレステロールも豊富です。高脂血症などの危険がありますし、腎臓や膵臓に不調がある子は、摂取量を抑える必要があります。
ほかにも、ビオチン(ビタミンB7)は体内で自力では生成できないものの、基本的にはドッグフードに配合されており、摂取が可能です。フードで足りない分は、腸内環境が整ってさえいれば、腸内細菌・腸内の微生物がビオチン(ビタミンB7)を生成するので問題ありません。

なーんだ、じゃあわざわざあげなくてもいいじゃん…
それに、そもそも、卵自体がアレルギーリスクの高めな食材ですから、フード以外でわざわざ与えないでいいのではないでしょうか?
ドッグフードから摂取するレベルの卵であれば、問題ない子の方が多いですし(体質によっては、ドッグフードですら、卵がダメ…という敏感な子もいるのは事実)、フードで食べる量くらいに関しては神経質になる必要はありません。
それより、わざわざプラスアルファで与える。これが問題です。栄養価が高いと聞いたら、「健康にいいんだろうし、与えよう」と安易に食べさせるのではなく、成分やデメリットを理解して適量を与える程度に抑える、もしくは、そもそもゆで卵は与えないのが一番ではないかと思います。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの⑦じゃがいも

ジャガイモは、一般的な市販のドッグフードや低アレルゲンフードなどでも、原材料として配合されています。もちろん、犬に与えても中毒性のある物質や健康を害するような成分は含まれていないため、与えることは可能です。しかし、やはり率先して与える必要はありません。
まず、特筆すべきジャガイモカの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | ビタミンC | 糖質 |
| 76kcal | 89.6g | 420mg | 11mg | 14.6g |

意外とヘルシーだし水分多いんだね。
カロリーもそこまで高くないし、水分も多く、ビタミンCなどもあるので、抗酸化作用は期待できそうなのですが、健康な犬にとっはビタミンCは、別に率先して与える必要はない成分です。
ビタミンCは体内で生成することができる成分です。胃腸が弱い子や、投薬中の子の場合、ビタミンCの酸味で余計に胃腸が荒れてしまうことがあります。気軽に「ビタミンCはいいんだ!」と与えるべきではありません。
カリウムも利尿作用やほてりを取るなんて言われますが、カリウムが多いのはいいことばかりではなく、心臓、腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。

食べられるからって与えるのは危険です!
そしてなにより、気になるのは糖質の多さ。食べ過ぎることで血液がドロドロになり太る原因になることがあります。炭水化物が多い食材の場合は、カロリー・脂質量だけで判断するのではなく、糖化しやすくないもの=炭水化物(糖質)が低いものかどうかを見ておかないといけません。
ドッグフードに配合されている場合は、メーカーがAAFCOの基準に則り、じゃがいもの栄養成分を加味したうえで、メリットを生かしながら配合しているので、特段問題はありませんが、個人でプラスアルファで与える食材として、ジャガイモはいかがなものでしょう?
芽の部分や、緑がかっている部分(光に当たって緑色になる)には、天然の毒素でもあるソラニンやチャコニンが含まれており、お腹を壊したり神経障害を起こしたりする危険もあります。取り除いたらOKといわれているものの、そんなリスクを負ってまで、愛犬に与えたいですか?
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの⑧メロン

甘くてジューシーなメロン。高級フルーツでもあります、赤肉のもの、緑の果肉のものなど、品種もたくさんありますよね。
人間の場合、酵素が強くて喉がかゆくなる・イガイガするという方もいて、食べられないなんて方もいるのですが、犬はどうなんでしょう?
まず、特筆すべきメロンの成分をご紹介します。(以下の数値は緑の果肉のメロンの、100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | βカロテン | 糖質 |
| 45kcal | 87.9g | 350mg | 140μg | 9.9g |

カロリーも低く、水分も多いですね
メロンの甘さは、まさに糖質の高さが影響しているのでしょう。決して糖質が低いフルーツではありません。これまでご紹介した食材でもお伝えしていますが、糖質が高いがゆえに、太りやすく肥満や肝機能などに心配がある子には注意が必要です。
糖質が高いと瞬発的に、体内に栄養を吸収させることはできますが、食べ過ぎることで血液がドロドロになり太る原因になることがあります。カロリー・脂質量だけで判断するのではなく、糖化しやすくないもの=炭水化物(糖質)が低いものかどうかを見ておかないといけません。
また、βカロテンは体内で、ビタミンAに変換されるのですが、ふつうにドッグフードを食べていたら十分体内に貯蔵しておけますし、運動量や年齢などによっては、摂取しすぎることでビタミンA中毒を引きを起こし、肝臓に負担がかかけ、健康問題につながるリスクがあります。

カリウムもこれまで紹介したとおり
カリウムには、余分な水分を体外に出して、血圧などを安定させる作用があるとはいえ、多いければいいというわけではなく、心臓、腎臓に持病があったり、犬種特有の疾患など注意しておきたいことがあったりする場合、摂取量を制限する必要があります。
なお、メロンには、ククミシンという酵素が含まれているのですが、これが喉のイガイガやかゆみを感じる原因です。人間だけでなく犬も同様で、腹痛や嘔吐、かゆみなどの原因になることがあります。
イネ化の植物などにくしゃみが出てしまいやすい子は、上記のアレルギー反応が出る危険があるので与えないに越したことはありません。もし、与えて不調が出た場合は、獣医の診察を受けるようにしてあげましょう。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの⑨山芋(大和芋)・長いも

栄養があり、消化もしやすいこともあり、滋養強壮には山芋(大和芋・ながいも)という考えの方は多いかもしれません。しかし、そんな「やまのいも」類も注意しておきたい点が多数あります。
まず、特筆すべき大和芋と長芋の成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
①大和芋(やまといも)
| カロリー | リン | カリウム | マグネシウム | 糖質 |
| 172kcal | 72mg | 590mg | 28mg | 25.6g |

わぁ!結構カロリー高いんだね!
②長芋(ながいも)
| カロリー | リン | カリウム | マグネシウム | 糖質 |
| 64kcal | 27mg | 430mg | 17mg | 12.9g |
長芋は大和芋ほど、こっくりしていないこともあって、カロリーは低めですがどうなんでしょうか?
まず、山芋や長芋は、皮膚疾患(カイカイ・皮膚炎など)をもつ犬には与えない方がいいです。人間でも、長芋や大和芋を食べて、口が痒くなったり、手に触れたところがかゆくなったりしたことがある人もいると思います。

人間だけじゃなく犬もカイカイ引き起こします
これはやまの芋の皮の付近に含まれる、シュウ酸カルシウムが原因で起こる症状で、犬の体についたり、食べて体内に取り込んだりすると、皮膚に負担がかかってしまう危険があるのです。もとから皮膚の不調がある子にとっては、言語道断、不要ではないでしょうか?
また、シュウ酸カルシウムは、尿路結晶や結石の原因にもなりますので、過去に尿路トラブルを経験していたり、犬種的に尿路トラブルに気を付けておきたいわんこの場合はやまのいも(大和芋や長芋)は与えない方が安心です。
しかも!マグネシウムもやまのいもには豊富なのですが、これも、過剰に摂取すると腸のトラブルや尿石症の原因になるものですので、やはり率先して愛犬に与える必要はないと思います。栄養がとれるからと与えていて、トラブルが起きたら本末転倒ではないでしょうか。
犬の管理栄養士が率先して与えない食べもの⑩洋ナシ(ラフランス)

日本の梨とは違い、独特な形状をしている洋ナシ。最近では、日本の農家さんでもラフランス(洋ナシ)の栽培をするケースが増えてきているようです。食べごろになると、皮に少しシワができ、指で押すと少し柔らかくなります。
まず、特筆すべき洋ナシの成分をご紹介します。(以下の数値は100gあたりの可食部の数値です)
| カロリー | 水分 | カリウム | ソルビトール | 糖質 |
| 48kcal | 84.9g | 140mg | 2.9g | 12.5g |

低カロリーで、たんぱく質ほぼありません
たんぱく質はほとんどない上に、ビタミン類もほぼない、にも関わらず糖質が高いことがおわかりいただけるでしょうか?この糖質には、糖アルコールの一種であるソルビトールがあり、少量であれば害はないとはいわれているものの、過剰摂取でお腹を壊す危険があります。
繰り返しになりますが、糖質の多さから、食べ過ぎることで血液がドロドロになり太る原因になることがありますので、カロリー・脂質量だけで判断するのではなく、糖化しやすくないもの=炭水化物(糖質)が低いものかどうかを見ておかないといけません。
そして、完熟していない洋梨には、体内で有毒物質に変化するアミグダリンが含まれており、嘔吐や下痢に見舞われてしまうことがあります。さほど嬉しい作用・効果があるわけでもない洋ナシなのに、これらのリスクを負ってまで、大事な愛犬に与えないでいいのではないでしょうか。
そもそも原則はおやつやトッピングは不要!ドッグフードで十分です

インターネットで調べて、良いと聞いたら、「そうなんだ!」と、あたかもいいことをしているように感じて、もっと愛犬のためにやってあげたいと思う飼い主さんは多いかもしれません。
しかし、メリットがあればデメリットもあります。必ず、愛犬にはそのメリットはどういいのか、デメリットの部分が愛犬にどう作用する危険があるのかを把握してから、愛犬に与えるようにしましょう。
デメリットの部分を正しく理解していなかったがために、飼い主さんご自身が愛犬を病気にさせたり、不調を引き起こさせたりするなんて誰が望んでいるでしょう?そんな飼い主さんはきっといないと思います。

ぼく、飼い主さんに寿命縮められるの?
インターネットで紹介されているような「食べて良い野菜」「食べて良いフルーツ」「与えて良い飲み物」などは、客寄せパンダ記事だらけです。一方的に良いように書いてあるだけで、あなたの愛犬に良いかどうかなんてわかりませんし、責任は取ってくれません。
食事に厳しい獣医などは、「食べる元気がある子にはおやつは与える必要はない」とはっきり名言している方だっています。実際に、私もトレーナーや獣医が監修した本などでも同様なことを言っている方を複数見てきました。
おやつやトッピングアイテムなどは、飼い主さんが上手に管理してあげられることです。かわいいから・欲しがるからとおやつを与え過ぎていないでしょうか。今回の記事が、そういった愛犬の食生活を見直すきっかけになると嬉しいです。