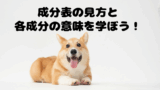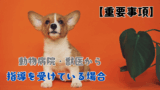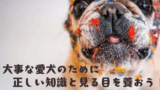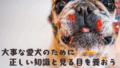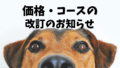犬にとって好ましい脂質と、たくさんは取らせたくない脂質があるのをご存知でしょうか?脂肪・脂質といっても種類や働きはさまざまで、脂質=悪ではなく、率先して摂取しておきたい・取るべき脂質があります。
また、「脂肪(脂質)」と聞くと、「脂(あぶら)」というイメージも手伝って、太る原因と考える方も多いかもしれませんが、必ずしも、脂肪(脂質)=太るというわけではありません。
しかし、あまり良いイメージがなく、極端にセーブしていたり、あるいは、そもそもの栄養素の働きをわからずに与えているフードで、知らぬ間に脂肪(脂質)過剰・欠乏に陥っている犬の相談をお受けするケースよくあります。

ダイエット中だとしても脂質は大事!
今回はそんな、過剰摂取もダメ、かといって、欠落してもダメな、犬の5大栄養素のひとつでもある「脂肪(脂質)」についてご紹介していきます。(※以後、脂肪という言い方ではなく、脂質と統一して記載していきますのでご了承ください。)
少しマニアックな栄養学な話になりますが、これを把握できていたら、ドッグフードの成分や原材料の説明に出てくる怪しい説明も理解でき、今後のフード選びの役にも立つはずです!難しく考えずに、愛犬のための知識として学んでみてください。
なお、いろいろ書いてありますが、犬の個体差もありますし、愛犬の体質を考えたフード選びや脂質について知りたい・相談したいという方は、お気軽にお問い合わせくださいね!※ 当サイトのアドバイスは有料です。無料で相談に回答するものではありません。
(※お問い合わせについて:当サイトからのメールが迷惑メールに振り分けられることがあるので、迷惑メールボックスもご確認ください)
「脂質」はよくない?太るから控えた方がいい?肥満の原因になる?

脂質は犬が健康生きていく上で欠かせない、五大栄養素のひとつです。そのため、太りそうだからと控えすぎはよくありません。バランスよく摂取する必要があります。また、どんな脂質を取るのか、どのくらい摂取するのかによっては、太る原因になるとも限りません。
脂質にあまり良い印象がない方は多いかもしれませんが、AAFCOでも犬が1日に摂取しておきたい脂質量は提示されており、この必要量よりも低い摂取量が続けば、健康を害する危険もあるので注意が必要です。
| パピー・繁殖・泌乳期 | 成犬 | |
| たんぱく質 | 22.5%以上 | 18.0%以上 |
| 脂質 | 8.5%以上 | 5.5%以上 |
| 繊維 | MAX4%(以下) | |
| 灰分 | *各成分によって異なる | |
| 水分 | ドライフードならMAX10%(以下) | |

上記は最低限の数字。それ以上必要です
もちろん、たくさん取り過ぎるのもよくないのですが、
などから、脂質過多・脂質欠乏がおき、皮膚や消化器に関するトラブルに陥る犬が多いのが現状です。
まず、飼い主さんは、脂質は犬にとって過剰摂取してもダメ、かといって、欠落してもダメな栄養素であるということを念頭に置いておいてくださいね。
そもそも「脂質」の働きとは?過剰摂取(過多)や欠落するとどうなる?

脂肪・脂質について詳しく話を進めていく前に、脂質の体内での役割をさっとご紹介しておきましょう。
- ビタミンの吸収を手伝う
- ホルモンバランスを保つ(パピーや繁殖期には特に重要)
- 関節・被毛・皮膚ケアに効果がある
- 抗アレルギー作用があり、免疫力がアップする
- 体温を保つ
などがあり、どれも健康には欠かせないものということがわかりますよね!
また、体内での働きという意味ではありませんが、フードの嗜好性を高めて食いつきをアップさせる、フード自体をなめらかな舌触りにするなどの役割もあり、フードに配合することでプラスになることもあるんですよ。

過剰摂取もダメ、欠落もダメ。バランスが大事!
ただし、過剰摂取は肥満の原因にもなりますし、その嗜好性ゆえに食べ過ぎや偏食の原因にもなりかねません。消化器に負担をかけることもありえるので、注意が必要です。逆に欠乏してしまうと、肌がカサカサになってしまったり、被毛の質が悪くなったりしてしまいます。
さらに、脂質は関節ケア成分の源ですので、関節のケガをしやすくなったり、炎症を抑えることができずに、カイカイや涙やけなどが治りにくくなったりしてしまうことも…。
このように、思いがけないトラブルに見舞われてしまう危険がありますので、脂質の摂取量やどんな脂質を摂取しておくべきかなどは、飼い主さんも注意してあげる必要があるのです。
犬の健康維持に必要な脂質とあまり多く与えたくない脂質がある?!

脂質には種類がたくさんあります。それぞれ詳しくみていくと、なにが良い脂質で、なにがあまりたくさん取らせたくない脂質かわかるので、少々マニアックなお話にはなってしまいますが、少し触れておきましょう。
まず、脂質を構成する「脂肪酸」単位で見ていきますと(脂肪酸の集合体が脂質というイメージです)、大きく分けて2つあります。
| 飽和脂肪酸 |
|
| 不飽和脂肪酸 |
|
上記のとおり、飽和脂肪酸は体内生成できるため、過剰に取る必要はありませんし、取りすぎるとコレステロールを増やしてしまいますのでご注意ください。飽和脂肪酸の多い原材料が配合されていて、脂質を補えているようなフードは避けた方がよいでしょう。
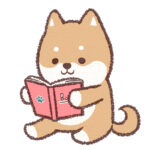
どんなものが飽和脂肪酸が多いの?
×たくさんとるのを避けたほうがいい飽和脂肪酸×
- サラダ油(パーム油)
- マーガリン
- バターなどの乳製品
- 牛肉、豚肉などの赤肉系の脂質
- ラードなど肉系の脂分や鶏皮などの脂部位
- 植物性油脂(ココナッツオイル含む、由来不明なもの)
- 動物性油脂(由来不明)
など
こういったものは、おやつや安価なフードに配合されがちなので、原材料を確認してみてくださいね。(100%絶対ダメということではありません。なお、不飽和脂肪酸が多い食材は次の項目でお伝えします)
一方、不飽和脂肪酸は体内生成できないということもあり、食べ物からでしか摂取できない脂質のことを指し、必須脂肪酸と呼ばれています。つまり、これこそが必要としている質の良い脂肪です!
さらに必須脂肪酸には、主に、
- オメガ3=α-リノレン酸・EPA・DHA
- オメガ6=リノール酸・アラキドン酸
の2つがあります。

こういったものは積極的に摂取しておきたい脂質です。
これらは抗アレルギー効果や抗炎症作用、健康な被毛の維持を促す成分なので、皮膚が弱く、カサカサになりがちだったり、フケが出やすくなったりしている子は、上記のような脂肪を取ることで、皮膚・血流が回復して、症状が改善することも期待できます。
このように「脂肪(脂肪酸)」「脂質」といっても、細分化してみていくと、特徴は違うことがお分かりいただけたでしょうか?
日本では超小型犬・小型犬なども人気ですので、関節ケアの意味でも体重管理が必要な子も多いかもしれませんが、必要な脂質はしっかりとって、間違えた脂質制限などはしないようにしておくとよいでしょう。
人間も犬の一番避けたい脂質「トランス脂肪酸」はあらゆる不調の原因に!

みなさん、一度は「トランス脂肪酸」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?トランス脂肪酸は、今回のテーマでもある、脂質・脂肪の中でも、一番厄介で気を付けたい脂質のです。
トランス脂肪酸については、ここで説明するととんでもない話になるので引用してご紹介しておきますと、
トランス脂肪酸には、天然に食品中に含まれているものと、油脂を加工・精製する工程でできるものがあります。
- 天然にできるもの
天然の不飽和脂肪酸は、通常シス型で存在します。しかし、牛や羊などの反芻(はんすう)動物では、胃の中の微生物の働きによって、トランス脂肪酸が作られます。そのため、牛肉や羊肉、牛乳や乳製品の中には微量のトランス脂肪酸が天然に含まれています。
- 油脂の加工・精製でできるもの
常温で液体の植物油や魚油から、半固体又は固体の油脂を製造する加工技術の一つに「水素添加」があります。水素を添加することで不飽和脂肪酸の二重結合の数が減り、飽和脂肪酸の割合が増えますが、これによってトランス脂肪酸ができることがあります。
- 部分的に水素添加した油脂を用いて作られたマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングや、それらを原材料に使ったパン、ケーキ、ドーナツなどの洋菓子、揚げ物などに、トランス脂肪酸が含まれているものがあります。
- 植物や魚からとった油を精製する工程で、好ましくない臭いを取り除くために高温で処理することにより、油に含まれているシス型の不飽和脂肪酸からトランス脂肪酸ができることがあります。そこで、サラダ油などの精製した植物油にも、微量のトランス脂肪酸が含まれているものがあります。

ふむふむ、避けたい脂質で説明したものだね!
特に気を付けたいのが、2つ目に上がっている人工的に作られたトランス脂肪酸です。善玉コレステロール(HDLコレステロール)を減らして、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を増やすことがわかっています。
マーガリンって、日本では普通に販売されていますが、海外では販売禁止になっていることすらあるほどの要注意食材だとご存知でしょうか?トランス脂肪酸を含む食材は、健康に害を及ぼす危険があるとWHOも認識しているんですよ。
人間の体力・免疫力をしても健康被害を及ぼしかねないトランス脂肪酸を、小さな体の犬に摂取させていていいのでしょうか?ただ添加物に気を付けるだけでは、こういった危険は見落としてしまいかねません。

日本って添加物大国なのですよ
犬のためのケーキやパンなど、人間も好きそうなおやつなどが販売されていますが、こういったものを与えるのは、愛犬の健康寿命を縮める危険があります。しかし、こういったものは嗜好性が高くて、好きな子も多いんですよね…。
とはいえ、上記に記載されている食材以外にも、生クリーム、チーズ、植物性油脂・食用調合油なども注意したい食材です。犬の誕生日などにもこういったものを与えてしまっていないでしょうか?
「たまにはいいよね」「うちの子チーズとかクリームとかの乳製品すきなのよね」と、人間の嗜好で犬にこういった食材を使ったおやつなどは与えがちですが、そういった危険も理解して、正しく健康管理をできる飼い主さんでいてくださいね。
必須脂肪酸と呼ばれる「不飽和脂肪酸」が多い食材ってどんなもの?
どんな食材に不飽和脂肪酸が多いのか、知っておきたいところですよね!
犬を太らせるだけではない、質のいい脂質(=不飽和脂肪酸が豊富)な食材には、以下のようなものがあります。
フードを選ぶ際に、原材料一覧を確認して、こういった食材が使用されていたら、

アレルギーがおさまって、皮膚や毛がきれいになりそう!
と思ってよいでしょう。(ただし、上記に挙げた食材にアレルギーがなければです。上記で挙げた食材は、アレルギーリスクは低いものばかりなので、そんなにアレルギーとして該当する子はいないと思いますが。)
カイカイ(皮膚炎)やアレルギー対策の犬の場合、サーモンや白身魚などのフードが推奨されるは、こういった理由からなんですね。
逆に、フードの説明で、上記のような質のいい脂質ではないもの(動物性油脂や植物性油脂)にもかかわらず・「脂質の品質」を気にすることなく、脂質源としてあたかもいいもののように書いてあるドッグフードは、しっかり見極めて選ばないようにしておきましょう。
意図していなところで脂質不足・脂質過多になっていることも?!

特に脂質を抑えているつもりでもなかったり、もしくは問題ない量で与えているつもりだったりする場合でも、脂質を取りすぎている、もしくは不足してしまっていることがあります。
よくあるのが以下の2つ。
たとえば、運動量が多くないのに、高たんぱくなフードを食べていると太ってしまうことがあるのですが、だからって給餌量を減らしていたら、必要な脂質までもが摂取できなくなってしまいます。たんぱく質摂取量は抑えられても、必要な脂質まで取れていないかもしれません。
逆に、運動量に見合わない高たんぱくフードを食べていることで、余ったたんぱく質が糖化して、脂質に変わり脂質オーバーになってしまうこともあります。または、運動量と適正体重を把握できておらず、フードの量が足りていないケースも。

正しく管理できていますか?感覚でやってませんか?
おやつを与えたいからとフードを減らして、必要な栄養が足りていないことはないでしょうか?もしくは、太るのが怖いからと量を減らしすぎていることもあり得ます。逆におやつの与え過ぎで、カロリーオーバーはしているものの、必要な栄養がとれていないこともあるものです。
このように、正しい給餌量(愛犬が1日に必要なカロリー摂取量)を把握できていないことにより、間違えた体重管理をしていたり、愛犬に良いと信じて疑わないで、合っていないフードを与え続けたりしていることから、脂質バランスが崩れてしまうことがあります。
ここでご紹介したような、脂質過剰による症状や、欠乏による症状が出ているようであれば、一度、正しい給餌量や適切なフードの見直しをしてみるとよいでしょう。
脂質を抑えた方が良い犬もいる!?でも、どんな状態の犬の場合?

過剰摂取も欠乏もよくないとはお伝えしたものの、脂質を極力抑えたほうがいいケースもあります。
ここでいう抑えたいケースというのは、単なる体重オーバー(肥満)などではなく、採血検査など、詳しい検査をした上での話、もしくは疾患がある場合の話です。具体的には、
などがありますが、これらは、しっかり動物病院で検査をしてこそわかることですので、まずは獣医の指示に従って然るべき検査など受けるようにしましょう。

簡単に判断できることではないので、まずは検査を!
なお、その後の愛犬の食事については、獣医から指定の療法食を出されることもありますし、今のフードのまま特に替えるなどはなく、投薬をしばらくして経過観察をするケースもあります。このあたりは、獣医判断の医学的な話ですので、当サイトの栄養学だけでは対応できません。
症状・数値レベルによっては状況も対処法も違ってきますので、独自判断で勝手にあれこれ対応しようとするのではなく、獣医に相談の上、決めるようにしてください。
当サイトでは、獣医から療法食を出されている間は、治療の妨げになりかねな栄養面のアドバイスは致しかねますのが、獣医から「脂質を抑えるよう」など指示があってフードを迷っている方などは、もちろん、相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
原材料をしっかり見て、成分表も確認してフードを選ぶのが大事!
クチコミやドッグフードのランキング評価が良いからといって、そのフードが本当に愛犬に合うかどうかはわかりません。いくら評判が良いフードであっても、犬にも個体差はあり、ちまたで人気なものがその子に必ずしもいいかはわからないものです。
そんなフードの選び方ではなく、しっかり信頼できる(食事を大事に考えている)獣医に相談したり、正しい犬の知識を持つ人(ネットや犬に詳しいというだけの人ではありません)に相談するなどをしてフードは選びましょう。

食事を重要視している獣医さんも結構多いんですよ
ただし、ペットショップのスタッフさんに相談するのは、正直、そのスタッフさんがどれほど食事の知識がある方かはわかりません。ペットの食事に詳しくないスタッフの方が多い気はします。店頭で扱っているもの以外紹介できませんしね。(※これはあくまで個人的な意見です)
インターネット、クチコミ、ペットショップのスタッフ、どう頼って、なにを信じるも飼い主さんの自由ではありますので、ここまでにしておきますが、飼い主さんには犬の正しい食生活の知識をつけて、愛犬に合うフードを選べるための知識をつけていけますように!